注文住宅の登記費用とは?相場と内訳を徹底解説【2025年最新版】
- 将士 飴本
- 8月7日
- 読了時間: 15分
注文住宅のマイホーム計画では「建物本体価格」や「土地代」に目が行きがちですが、実際に家を所有するためには“登記費用”という大きな諸経費が発生します。
本記事では最新2025年相場データ・登記の全手続きフロー・費用の内訳・節約術・プロのアドバイスやリアルな体験談まで徹底解説。
家づくり初心者も経験者も「知らなきゃ損する」注文住宅の登記費用ガイドの決定版です。
目次
1: 注文住宅の登記費用とは?
1-1: 登記費用の基本的な理解
1-2: 注文住宅にかかる諸費用の全容
1-3: 登記の必要性とその流れ
2: 注文住宅の登記費用の相場
2-1: 新築時の登記費用の相場
2-2: 土地と建物の登記費用について
2-3: 費用シミュレーションの手法
3: 登記手続きに関する詳細
3-1: 所有権移転登記と所有権保存登記の違い
3-2: 抵当権設定登記の流れ
3-3: 必要書類と申請の手順
4: 登記費用の構成要素
4-1: 登録免許税とは?
4-2: 司法書士への報酬と手数料
4-3: 印紙税とその他の諸費用
5-1: 新築住宅の標準的な費用例
5-2: 登記費用を節約する方法
5-3: 費用負担を軽減するための工夫
6-1: 登記手続きを行わないリスク
6-2: よくあるトラブル事例
6-3: プロに依頼するメリットとデメリット
7: 結論と今後の選択肢
7-1: 費用を把握し、計画的に家づくりを進める
7-2: 必要な手続きをスムーズに行うために
7-3: 専門家を頼る基準と信頼できる選び方

1: 注文住宅の登記費用とは?
1-1: 登記費用の基本的な理解
注文住宅でマイホームを取得するとき、「登記」は絶対に欠かせないプロセスです。登記とは、法務局に「自分がこの土地・建物の所有者だ」と正式に登録する手続きであり、住宅ローンの利用や不動産の売買・相続の際にも重要な役割を果たします。
登記を行うことで、第三者に対して所有権を証明できる
ローン返済中は「抵当権」も同時に登記されるのが一般的
万一登記を怠ると、所有権トラブルや資産価値喪失リスクにも直結
【プロ視点】
「登記は“自分の財産を守る”最重要ポイント。後回しにせず、引き渡し・融資実行と同時に確実に完了させましょう」
1-2: 注文住宅にかかる諸費用の全容
注文住宅取得時には「登記費用」以外にも多くの諸経費が発生します。たとえば「火災保険料」「引越し費用」「ローン事務手数料」「登記以外の各種税金」など。登記費用は“諸費用総額の2~4割”を占めることも多く、資金計画時にしっかり確保が必要です。
費用項目 | 目安金額 | ポイント |
登記費用 | 30~60万円 | 土地・建物・抵当権設定で金額が異なる |
火災・地震保険 | 15~30万円 | 補償内容や保険期間で差 |
ローン手数料 | 5~10万円 | 金融機関による |
印紙税 | 1~5万円 | 契約金額によって変動 |
引越し・新生活用品 | 10~30万円 | 距離・家族人数で差 |
【実体験】
「予想以上に“諸費用”が膨らみ、登記費用だけで50万円超。事前の見積もりと“諸費用明細”のチェックが不可欠です」
\➡ 関連記事:住宅購入時に知っておくべき諸費用の全貌!
1-3: 登記の必要性とその流れ
登記の主な流れは、土地登記 → 建物登記 → 抵当権登記というステップが一般的です。
土地の所有権移転登記(売主→買主、または親からの贈与等)
建物の所有権保存登記(新築の場合は“保存登記”)
抵当権設定登記(住宅ローンを利用する場合)
申請は司法書士に依頼するのが一般的(自分で手続きも可だが難易度高)
「登記完了証」をもって“正式な所有者”と認められる
2: 注文住宅の登記費用の相場

2-1: 新築時の登記費用の相場
注文住宅を新築する際の登記費用は、全国平均で約30万円〜60万円が相場です。この金額には**「土地の登記」「建物の登記」「抵当権設定の登記」**の3つが含まれますが、土地を新たに購入するか、実家土地を活用するかによっても変動します。
項目 | 相場(全国平均) | 備考 |
土地の所有権移転登記 | 10~25万円 | 土地購入時のみ。登記済み土地なら不要 |
建物の所有権保存登記 | 6~15万円 | 新築時は必須 |
抵当権設定登記 | 6~12万円 | 住宅ローン利用時は必須 |
司法書士報酬(手数料含む) | 8~18万円 | 手続き一式。地域・物件規模で増減 |
合計 | 30~60万円 | 土地あり注文住宅・住宅ローン有を想定 |
【実体験】
「首都圏で土地付き注文住宅を建てた際、登記関連の見積もりが総額57万円。内訳明細を見て“司法書士報酬”の幅の大きさに驚いた」(40代・会社員)
2-2: 土地と建物の登記費用について
■ 土地の登記
土地購入時は「所有権移転登記」が必須(親族から贈与・相続の場合も必要)。
登録免許税は「土地の固定資産評価額×2%」が原則(軽減措置適用で1.5%などになる場合もあり)。
都市部の評価額が高いほど、登記費用も高くなる。
■ 建物の登記
新築の場合は「所有権保存登記」が必要(登録免許税=評価額×0.4%が目安、軽減特例あり)。
建物評価額は“新築時の建築確認通知書等”に基づいて決まる。
木造と鉄筋コンクリート造、建物規模で評価額が大きく異なる。
登記種別 | 課税標準・税率 | 相場目安(例) |
土地の移転登記 | 評価額×2.0% | 12万円(評価額600万円時) |
建物の保存登記 | 評価額×0.4% | 3万円(評価額750万円時) |
抵当権設定登記 | 借入額×0.4% | 6万円(借入1500万円時) |
\➡ 関連記事:土地探し成功のカギは〇〇!意外なポイントとは
2-3: 費用シミュレーションの手法
注文住宅の登記費用は、物件価格・評価額・借入額によっても大きく変動します。実際の資金計画時は“個別シミュレーション”が必須です。
▼ シミュレーション例
土地評価額:1,000万円、建物評価額:1,200万円、住宅ローン:2,000万円の場合
土地の所有権移転登記:1,000万円×2.0%=20万円
建物の所有権保存登記:1,200万円×0.4%=4.8万円
抵当権設定登記:2,000万円×0.4%=8万円
司法書士報酬・手数料:15万円
合計:47.8万円
▼ シミュレーション時のポイント
評価額・借入額は「固定資産評価証明書」や「ローン仮審査書類」で確認
司法書士に「概算見積もり」を依頼し、明細を事前にもらう
ローン借り入れの有無や名義(夫婦共有等)でも費用が変わる
【プロ視点】
「“登記費用は建築費の2%前後”がざっくり目安。実際は“物件評価額”や“借入金額”次第で大きく上下するので、契約前に必ず細かくシミュレーションしよう」
3: 登記手続きに関する詳細

3-1: 所有権移転登記と所有権保存登記の違い
登記の基本は「所有権移転登記」と「所有権保存登記」の2つ。注文住宅の場合は、「土地」と「建物」で登記の種類が異なります。
項目 | 所有権移転登記 | 所有権保存登記 |
主なタイミング | 土地を購入した時、親族間贈与、相続 | 新築の建物完成時(初めて登記される時) |
必要なケース | 売買・贈与・相続で名義を変える時 | 新築時、誰の名義もない建物に所有権を主張する時 |
主な必要書類 | 売買契約書、登記識別情報、印鑑証明など | 建築確認済証、工事完了引渡証明書、印鑑証明など |
登録免許税の税率 | 評価額の2.0%(軽減措置あり1.5%等) | 評価額の0.4% |
土地の購入=「所有権移転登記」
新築建物=「所有権保存登記」
相続・贈与でも移転登記が必要
【現場エピソード】
「中古住宅の購入は“土地+建物両方の移転登記”。新築は“土地移転+建物保存”。“どちらの手続きが必要か”をよく確認してください」
3-2: 抵当権設定登記の流れ
住宅ローンを利用する場合、金融機関は「返済できなかった場合に備えて、担保として家と土地を押さえる権利=抵当権」を登記します。これが「抵当権設定登記」です。
▼ 流れと注意点
住宅ローン審査通過後、融資実行と同時に手続き
必要書類(ローン契約書・印鑑証明・住民票など)を司法書士に提出
司法書士が法務局へ登記申請
登記が完了しないと融資実行されない(引渡し不可)ケースが多い
費用項目 | 金額目安 | ポイント |
登録免許税 | 借入金額の0.4% | 各種軽減措置がないことが多い |
司法書士報酬 | 2万~6万円 | 報酬は登記件数や金融機関で増減 |
【プロの実感】
「抵当権設定は“ローン実行直前のバタバタ時期”に必須。必要書類の“もれ”で引き渡しが遅れたり、登記完了証をなくして後々困るケースも。引越し前に複数コピー保存を!」
3-3: 必要書類と申請の手順
登記申請は複雑なので司法書士に依頼が一般的ですが、自分で申請(いわゆる「本人申請」)も可能です。しかし、記載ミスや書類不足で「補正命令」や「申請却下」になると最悪「物件引渡し延期」も。
▼ 主要な必要書類
所有権移転登記
売買契約書/登記識別情報(権利証)/印鑑証明/住民票/固定資産評価証明書 など
所有権保存登記
建築確認済証/工事完了引渡証明書/住民票/印鑑証明 など
抵当権設定登記
ローン契約書/銀行からの委任状/印鑑証明/住民票 など
▼ 申請手順(流れ)
必要書類の収集・準備(早めに!)
司法書士へ依頼 or 本人で法務局へ持参
法務局で申請・手数料納付
登記完了証・登記識別情報を受け取る
必要なら金融機関や売主へ報告・引渡し手続き
【体験談】
「住民票の本籍地記載や、評価証明書の“発行日数”に要注意。役所の混雑で取得に1週間かかり、ギリギリで間に合いました…」
4: 登記費用の構成要素

4-1: 登録免許税とは?
「登録免許税」は、不動産登記の際に必ずかかる“国に納める税金”です。登記の種類ごとに税率や計算方法が異なるため、申請内容を正確に把握しておくことが大切です。
登記種別 | 税率(2025年) | 算出方法例 | 備考 |
所有権移転登記 | 評価額×2.0% | 土地1,000万円→20万円 | 軽減措置で1.5%もあり |
所有権保存登記 | 評価額×0.4% | 建物1,200万円→4.8万円 | 新築住宅は軽減あり |
抵当権設定登記 | 借入額×0.4% | 借入2,000万円→8万円 | ローン利用時は必須 |
【プロのポイント】
「評価額は“購入価格”ではなく、“固定資産税評価額”がベース。購入金額とズレるので、事前に市町村役場で“評価証明書”を取り寄せておくと安心」
4-2: 司法書士への報酬と手数料
登記申請のほとんどは司法書士に依頼するのが一般的です。報酬額は「登記件数」「地域」「物件規模」によって幅があるため、必ず見積もりをとり比較検討しましょう。
項目 | 目安報酬(全国平均) | 備考・アドバイス |
所有権移転登記 | 3~6万円 | 土地取引・中古住宅購入など |
所有権保存登記 | 2~5万円 | 新築住宅建物 |
抵当権設定登記 | 2~4万円 | ローン利用時 |
必要書類取得代行・実費 | 1~3万円 | 住民票・評価証明書・交通費等を含むことも |
合計 | 8~18万円 | 複数件まとめて依頼で割引もあり |
【実体験】
「複数の司法書士に見積もりをとった結果、報酬の差が5万円以上も。登記費用は“明細書の有無”や“手数料に含まれる実費範囲”まで要確認」
4-3: 印紙税とその他の諸費用
登記そのものには印紙税は不要ですが、「建築請負契約書」や「ローン契約書」には印紙税が発生します。
契約金額 | 建築請負契約の 印紙税 | ローン契約 の印紙税 | 備考 |
500万円超~1,000万円以下 | 1万円 | 2万円 | 記載金額で決まる |
1,000万円超~5,000万円以下 | 2万円 | 2万円 | 電子契約は非課税のケースも |
5,000万円超~1億円以下 | 6万円 | 6万円 |
契約ごとに原則1通ずつ貼付が必要
登記費用以外にも「証明書発行手数料」「交通費」などの実費がかかることも
【アドバイス】
「印紙税は“印紙の貼り忘れ”や“二重貼付”による無駄な出費が意外と多い。電子契約の活用や、必要枚数を司法書士とダブルチェックを」
5: どのくらいの費用がかかるか?

5-1: 新築住宅の標準的な費用例
注文住宅の登記費用は、土地・建物の評価額やローン借入額、司法書士報酬、地域差などで変動します。ここでは【2025年の標準的な費用例】を示します。
項目 | 都市部(目安) | 地方(目安) | 備考 |
土地の移転登記 | 20万円 | 10万円 | 土地評価額で差が大きい |
建物の保存登記 | 5万円 | 3万円 | 建物評価額・構造で変動 |
抵当権設定登記 | 8万円 | 6万円 | ローン借入額で変動 |
司法書士報酬 | 15万円 | 10万円 | 地域・依頼件数で差 |
印紙税等・その他 | 2万円 | 1万円 | ローン契約・証明書発行手数料等 |
合計 | 50万円 | 30万円 | 土地・建物・ローン全て登記する場合 |
【体験談】
「首都圏で土地付き注文住宅を購入。登記関係でトータル52万円かかったが、明細を細かくチェックして“想定外の追加費用”がなかったのが安心材料でした。」
\➡ 関連記事:住宅見積もり診断の極意!無駄を省く最適チェックリスト
5-2: 登記費用を節約する方法
登記費用は「節約しづらい」と思われがちですが、工夫次第で数万円単位のコストダウンが可能です。
複数の司法書士に見積もりを取る(報酬や手数料の競争が発生)
土地・建物の名義を絞る(共有名義は登記件数増=費用増)
住宅ローン控除や登録免許税の軽減措置を最大活用する
“本人申請”にチャレンジ(難易度高いが、数万円~10万円以上節約も)
不要なオプションや手続き代行費の見直し
節約アイデア | 効果の目安 | 備考 |
複数の司法書士で相見積もり | 2~5万円 | 大きな物件ほど差額も大きい |
本人申請で一部登記を自力申請 | 5~10万円 | 申請ミスやリスクも考慮、プロ推奨は“報酬交渉” |
控除・軽減制度フル活用 | 2~8万円 | 新築住宅・一定要件で大きく差が出る |
【プロのアドバイス】
「本人申請はハードルが高いですが、最近は一部登記のみ自力で行い、複雑な部分だけ司法書士に任せるハイブリッド型も人気。失敗しないためには“登記全体の設計図”を作ってから取りかかりましょう。」
5-3: 費用負担を軽減するための工夫
登記費用の一括負担が厳しい場合や、家計負担を少しでも抑えたい場合は以下の工夫が効果的です。
諸費用込み住宅ローンを活用する(登記費用もローンに組み込める場合あり)
自治体の独自補助金や住宅取得支援制度の活用
登記費用の「仮払い」や分割払い対応の司法書士事務所も増加中
住宅会社・金融機関のキャンペーンや提携特典を活用
【アドバイス】
「工務店が提携している司法書士経由で“登記費用ローン可”だったので、現金負担を抑えて無理なく家計管理できました。」
6: 登記に関するトラブルと解決策
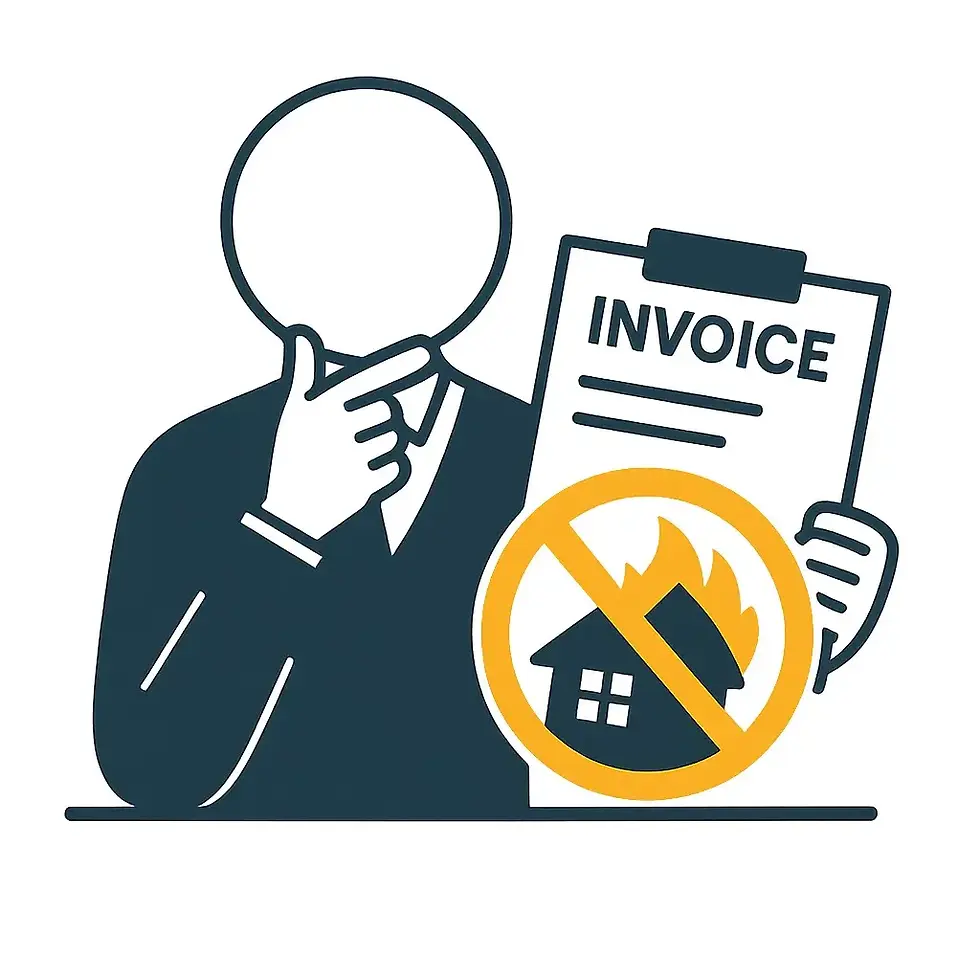
6-1: 登記手続きを行わないリスク
登記を怠る、あるいは「登記内容に誤りがある」場合、重大なトラブルや法的リスクにつながります。
所有権の証明ができず、他人に不動産を奪われるリスク
住宅ローン実行不可(抵当権設定できず、融資を受けられない)
相続や贈与、売却時に大きなトラブルとなる
課税上の不利益や、固定資産税の納付者が誤ることもある
【実体験】
「知人は建物保存登記を忘れていて、売却時に法務局で発覚。結果的に買主への引渡しが遅れ、追加費用が発生してしまいました」
6-2: よくあるトラブル事例
実際の現場で多い「登記手続きのトラブル」は以下の通りです。
トラブル内容 | 原因と背景 | 対策・解決策 |
必要書類の不足・誤記 | 住民票・印鑑証明の期限切れ、誤字脱字など | 必要書類リストを事前確認、最新の書類を準備 |
登録免許税の納付漏れ | 振込・納付が間に合わず登記が遅延 | 司法書士に納付代行依頼、余裕を持ったスケジュール |
司法書士とのコミュニケーション不足 | 費用明細・手続き内容の説明不足 | 必ず複数回の打ち合わせ・明細の確認を徹底 |
名義・共有持分の設定ミス | 家族間の話し合い不足、相続時の見落とし | 契約前に名義人・持分割合を家族で話し合い、専門家にも相談 |
抵当権抹消忘れ | ローン完済後も抵当権が残っているケース | ローン完済時に必ず司法書士に依頼、登記簿の確認も定期的に |
【プロのアドバイス】
「“書類の期限切れ”と“共有名義ミス”は特に多い。登記内容に疑問があれば必ず司法書士・不動産会社に早めに確認を」
\➡ 関連記事:注文住宅の見積もりでよくあるトラブル事例と正しい対策方法
6-3: プロに依頼するメリットとデメリット
登記手続きを「自分で行う(本人申請)」か「司法書士などの専門家に依頼する」かは、それぞれメリット・デメリットがあります。
項目 | 本人申請 | 司法書士等プロ依頼 |
メリット | 費用節約、手続きフローの理解が深まる | ミスが少なく確実、法的リスクを防止、スムーズな進行 |
デメリット | 書類ミス・補正命令・申請却下リスク、平日に役所通いが必要 | 報酬がかかる(8~18万円程度)、司法書士との打合せが必要 |
【アドバイス】
「知り合いは“節約”目的で本人申請したが、必要書類の誤記載で補正命令。結局、期限内に間に合わず司法書士に再依頼して二度手間になったそうです」
7: 結論と今後の選択肢
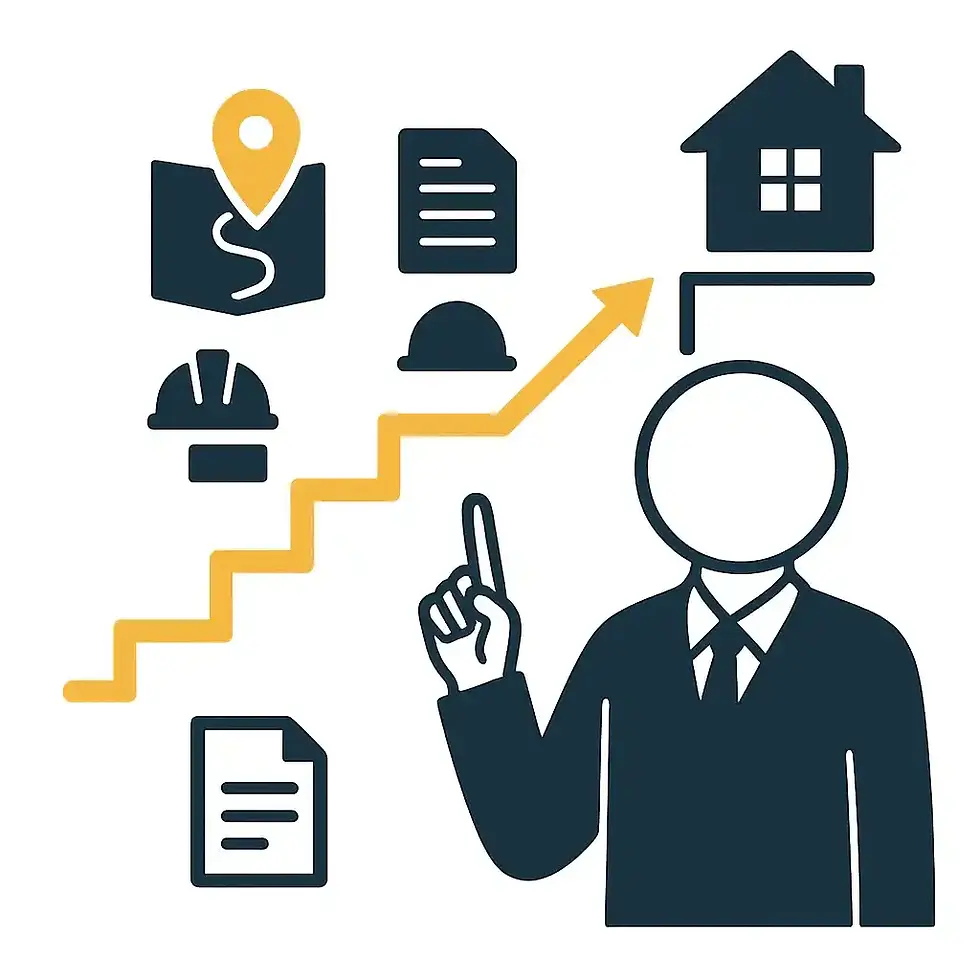
7-1: 費用を把握し、計画的に家づくりを進める
注文住宅における登記費用は、建物本体や土地代と比べると目立ちにくいですが、「家づくりの最後に確実に必要となる経費」です。着工前から資金計画に“登記費用”を組み込んでおくことが、想定外の出費やトラブル防止に直結します。
資金計画シートや住宅会社の資金相談サービスを活用
「見積書の明細」「登記費用の内訳」を必ず書面で確認
不明点や疑問点は“都度質問”し、曖昧にしない
【実体験】
「契約前に司法書士の見積もり明細まで確認していたので、“こんなに高いの?”と驚かず済みました。やはり“事前の明細確認”は絶対です」
7-2: 必要な手続きをスムーズに行うために
登記に必要な書類は、“揃え忘れ”や“記入ミス”によるトラブルが多いもの。司法書士や不動産会社と密に連絡を取りながら、「必要書類リスト」を作り、抜け・漏れがないようダブルチェックしましょう。
▼ 登記手続きチェックリスト(一例)
登記申請に必要な全書類の事前確認
住民票・印鑑証明書は最新か、期限は切れていないか
契約書・評価証明・委任状等の“原本”を確保
家族間で“名義”や“持分割合”の認識にズレがないか
司法書士の報酬明細・納付予定日を確認済み
【プロのアドバイス】
「書類は“前日に慌てて集める”のではなく、早め早めの準備が肝心。“何をいつまでに揃えるか”を計画表で管理しましょう」
7-3: 専門家を頼る基準と信頼できる選び方
登記手続きを確実に、かつ安心して進めるためには、信頼できる司法書士・専門家選びが重要です。
▼ 専門家を選ぶ際のポイント
複数の司法書士から見積もりを取得し、報酬・対応を比較
説明がわかりやすく、レスポンスが早い人を選ぶ
ネットの評判や口コミも参考にしつつ、“実際に会って相談”するのがベスト
住宅会社や金融機関と提携している司法書士なら実績豊富なことが多い
【アドバイス】
「見積もり対応が早く、細かい疑問にも丁寧に答えてくれる司法書士さんはやっぱり安心感が違いました。家づくりは“人選び”が本当に大切だと実感!」
まとめ
注文住宅の登記費用は、「知識があるか・早めに行動するか」でトータルの満足度が大きく変わります。“見積もりの内訳を明確にし、必要書類を事前に揃え、信頼できる専門家を選ぶ”―この3点を押さえることで、登記の失敗や後悔はほぼ防げます。費用面でも精神的にも、余裕を持った家づくり計画を目指しましょう。
見積もりに不安があるなら「見積もりバンク」へ
見積書にはプロでも見落とすポイントが多く存在します。
だからこそ、第三者の視点でチェックすることが大切です。
見積もりバンクでは、注文住宅の見積書を中立的な立場で比較・診断し、
安心できる家づくりをサポートします。
不安な見積もりのチェック
他社との比較で見えてくるポイント
契約前のセカンドオピニオンとして
\➡ 詳しくは見積もりバンク公式サイトをご覧ください。
-26.webp)



