気密性の高い家のデメリットとは?快適さの裏にある意外な落とし穴を解説
- 見積もりバンク担当者

- 2025年5月12日
- 読了時間: 26分
更新日:4 日前
更新日:2026年01月30日
住宅業界では「気密性の高い家=高性能住宅」として注目されています。確かに、冬は暖かく夏は涼しい、省エネで快適な住環境を実現できますが、一方で「息苦しい」「結露が増えた」「臭いがこもる」など、気密性の高さゆえのデメリットを実感する人も少なくありません。
この記事では、
✅ 気密性が高い家の基本構造と仕組み
✅ 実際に起こりやすいデメリット・トラブル事例
✅ 後悔しないための設計・換気・暮らし方のコツを、住宅営業経験と施工現場の実例をもとに詳しく解説します。
「気密性を上げれば上げるほど良いのか?」という疑問を、実務者の視点でわかりやすく整理しました。

目次
1-1. 「気密性」と「断熱性」の違い
1-2. C値(相当隙間面積)とは何か?
1-3. なぜ今“高気密住宅”が増えているのか
2-1. 冬暖かく夏涼しい省エネ住宅になる
2-2. 光熱費が下がる・温度ムラが少ない
2-3. 外気・騒音・花粉の侵入を防げる
3-1. 換気不足による結露・カビのリスク
3-2. 室内の臭い・湿気がこもりやすい
3-3. 設計ミスで“息苦しい家”になることも
4-1. 結露による壁内腐食・断熱材の劣化
4-2. 換気システムの不具合による空気汚染
4-3. ペット・調理臭が抜けにくい環境
5-1. 第1種換気(熱交換換気)システムの導入
5-2. 換気口・吸気経路を定期点検する
5-3. 適度な開放感を意識した設計
5-4. “高気密=高断熱”を前提にしすぎない
5-5. 暮らし方で気密性を活かす工夫
6-1. 設計士・工務店の気密測定実績を確認
6-2. 実際のC値・UA値を数値でチェック
6-3. メンテナンス費・換気コストも比較する
6-4. 建材のVOC対策を確認
6-5. 施工体制・測定精度を重視する
7-1. “呼吸する家”という考え方
7-2. 性能を目的化しないことが重要
7-3. 地域・暮らしに合わせた気密レベルを選ぶ
7-4. 後悔しない3原則と施工精度チェック
7-5. 著者からのメッセージ|性能より暮らし

「気密性の高い家」とは、家の隙間を極力減らし、外気が侵入せず、室内の空気が逃げにくい住宅構造を指します。冬の寒さや夏の暑さを和らげ、省エネ効果が高いとして人気ですが、仕組みを誤解したまま建てると“快適なはずの家が息苦しい”というケースも。まずは、気密性の意味と断熱性との違い、そして高気密住宅が増えている背景を理解しましょう。
1-1. 「気密性」と「断熱性」の違い
項目 | 気密性 | 断熱性 |
意味 | 隙間をなくして空気の出入りを防ぐ性能 | 熱を通しにくくする性能 |
目的 | 外気や湿気・ホコリの侵入を防ぐ | 室温を一定に保つ |
測定指標 | C値(相当隙間面積) | UA値(外皮平均熱貫流率) |
関係性 | どちらか一方だけでは効果が不十分 | 両立させることで省エネ性・快適性が最大化 |
つまり、気密性=「空気の通り道を塞ぐ」こと、断熱性=「熱の移動を防ぐ」こと。この2つがバランス良く保たれて初めて“冬暖かく夏涼しい家”になります。
💡 プロのアドバイス
断熱性だけ高くても隙間風があれば熱が逃げます。逆に気密性だけ高くても換気が悪ければ結露や空気汚染が起こります。**「高気密・高断熱セット」**が理想であり、どちらか一方の性能を誇張する住宅会社には注意が必要です。
1-2. C値(相当隙間面積)とは何か?
「C値(シーチ)」とは、住宅全体にどれだけの“隙間”があるかを数値化したものです。数値が小さいほど隙間が少なく、気密性能が高い家とされます。
C値の目安 | 評価 |
0.5以下 | 非常に高気密(北海道・寒冷地レベル) |
1.0〜2.0 | 省エネ住宅基準(多くの注文住宅で採用) |
5.0以上 | 隙間が多く、冷暖房効率が悪い |
C値は「家1㎡あたりの隙間面積(㎠)」で表され、専門業者が気密測定試験(ブロワードアテスト)によって測定します。ただし、C値が良くても実際の施工品質が悪ければ意味がありません。
💬 実例紹介
広島県の注文住宅でC値0.4を達成したが、換気システムの設計が甘く、湿気がこもるトラブルが発生。「数値だけでは快適さを保証しない」ことが明らかになりました。
1-3. なぜ今“高気密住宅”が増えているのか
高気密住宅が注目されている背景には、次の3つの要因があります。
✅ ① エネルギーコストの高騰
電気代・ガス代の上昇により、省エネ性能を重視する家庭が増加。気密性を高めて冷暖房効率を上げることが家計防衛の一環になっています。
✅ ② ZEH・長期優良住宅など国の基準強化
政府が推進する「脱炭素住宅」政策の影響で、C値・UA値の基準をクリアする設計が標準化。ハウスメーカーや工務店も高気密化を標準仕様にする傾向があります。
✅ ③ 生活の快適さ・健康志向の高まり
花粉・PM2.5・外気汚染などの影響を受けにくく、アレルギー対策住宅としても人気です。ただし、気密性を高めるほど“空気がこもるリスク”も同時に上昇します。
🏡 専門家コメント
「高気密=良い家」と思い込むのは危険です。高気密住宅こそ、設計段階での換気システムの計画性が命。数値ではなく、実際の生活空間での快適さを評価すべきです。— 住宅性能診断士(建築コストアドバイザー)

「気密性の高い家」は、住宅の性能向上の象徴とされ、快適さ・健康・省エネの3拍子が揃う住宅として注目されています。ここでは、実際に暮らしてみて感じる代表的なメリットを整理します。
2-1. 冬暖かく夏涼しい省エネ住宅になる
気密性の高い家の最大の利点は、室内温度の安定性です。冷暖房の効率が高く、エアコンの設定温度を控えめにしても快適に過ごせます。
季節 | 効果の内容 | 具体的なメリット |
冬 | 暖房の熱が逃げにくい | 足元が冷えにくく、結露が少ない |
夏 | 外気の熱気が入りにくい | エアコンが効きやすく、室温ムラが減る |
通年 | 湿度変化が緩やか | カビ・ダニの発生を抑えられる |
💡 ポイント
国土交通省の「住宅性能表示制度」でも、断熱等性能等級・一次エネルギー消費量等級が重視されています。高気密住宅は、これらを高レベルで満たす設計が基本です。
🧰 実例
30坪の木造高気密住宅(C値0.5/UA値0.46)で、従来住宅と比べて年間冷暖房費が約25〜30%削減されたというデータもあります(出典:一般社団法人 住宅性能評価推進協会)。
2-2. 光熱費が下がる・温度ムラが少ない
気密性を高めると、冷暖房のロスが少なくなるため、電気代・ガス代の節約につながります。また、リビングと廊下・脱衣所などで温度差が小さくなるため、「ヒートショック」リスクの軽減にも効果的です。
項目 | 高気密住宅 | 一般住宅(C値5.0程度) |
冷暖房費(年間) | 約8〜10万円程度 | 約11〜13万円程度 |
部屋ごとの温度差 | 1〜2℃ | 4〜6℃ |
結露の発生 | 少ない | 多い(窓・壁際) |
👨🔧 専門家コメント
「光熱費が下がる=健康にもつながる」点が見逃せません。家全体の温度が一定になることで、体感ストレスの少ない生活ができます。
🏡 施主の声
「冬でも素足で歩ける家になりました。エアコンの使用時間が減り、空気の乾燥も気にならなくなりました。」
👇もっと深く知りたい方はこちら
2-3. 外気・騒音・花粉の侵入を防げる
気密性を高めることで、外の汚染物質や騒音を遮断できるのも大きな利点です。とくに都市部や幹線道路沿いでは、防音性能の高さが快適性に直結します。
✅ 外気侵入を防ぐメリット
花粉・PM2.5・排気ガスなどを大幅にカット
外気温・湿気の影響を受けにくい
室内空気の清浄度を保ちやすい
✅ 騒音低減効果
外部騒音を約30〜40%軽減(遮音サッシ併用時)
深夜・早朝でも快適な睡眠環境を維持できる
テレワーク・在宅ワークにも適した静音性能
🧱 プロ視点の補足
高気密住宅は「防音性能を求める人」にも最適です。外壁やサッシの隙間が少ないため、遮音性能が自然に高まるのです。ただし、防音目的で建てる場合は「壁内吸音材」や「トリプルサッシ」も検討が必要です。
2-4. アレルギー・健康への好影響
気密性が高い家は、外からのホコリや花粉が入りにくく、室内環境が安定します。さらに、計画換気システムを併用することで、アレルギー症状や喘息の悪化を防ぐ効果も期待できます。
効果 | 内容 |
花粉症軽減 | 外気の流入を遮断+フィルター換気 |
PM2.5対策 | 微粒子を取り除く換気フィルターを通過 |
カビ・ダニ抑制 | 湿度コントロールにより繁殖を防止 |
👩⚕️ 医療専門家のコメント
「気密性の高い家は、アレルギー疾患の子どもがいる家庭にも向いています。換気計画を正しく行えば、空気の質を高く保てます。」
🧩 まとめ:気密性の高さは「快適な暮らし」につながる
高気密住宅のメリットは、単なる「暖かい・静か」という快適性にとどまりません。健康・経済・環境の3つの側面で持続的な価値を生む点が魅力です。
分野 | メリット |
快適性 | 温度ムラ・結露が少なく快適 |
経済性 | 光熱費・冷暖房費の削減 |
健康性 | 空気清浄・花粉防止で健康維持 |
環境性 | CO₂削減・省エネ基準対応 |
💬 プロのアドバイス
気密性は「暮らしの質」を左右する重要な性能ですが、高すぎても問題です。次章では、「気密性の高い家のデメリット」を詳しく掘り下げます。実際に“後悔した施主の事例”も交えて、見落とされがちなリスクを紹介します。

気密性が高い家は、確かに光熱費の削減や快適性に優れています。しかし、「メリットの裏にはデメリットがある」のも事実です。とくに、換気・湿度・空気の質に関する問題は、設計段階のわずかなミスが後の生活に大きな影響を与えることがあります。
3-1. 換気不足による結露・カビのリスク
気密性が高い住宅では、自然な空気の流れ(隙間風)がほとんど発生しません。そのため、機械換気がうまく機能しないと、湿気がこもり「壁内結露」や「カビ発生」のリスクが高まります。
❌ よくあるトラブル例
冬場、窓際やクローゼット内の結露が多発
壁内に湿気が溜まり、断熱材が黒ずむ
畳・カーテン裏・押入れのカビ臭
アレルギーや喘息が悪化するケースも
原因 | 内容 |
換気経路の設計ミス | 空気の流れが偏って湿気が滞留 |
結露対策不足 | サッシや断熱層の温度差で水滴が発生 |
換気システム停止 | 冬場の電気代節約で換気を止めてしまう |
💬 専門家の声
「結露は“断熱不足”よりも“気密と換気のバランス不足”で起きることが多いです。気密性が高いほど、換気計画の重要性が増すことを理解しておきましょう。」
3-2. 室内の臭い・湿気がこもりやすい
気密住宅では、料理・タバコ・ペット・洗濯物の臭いなどが外に逃げにくいという問題があります。また、湿度が高い地域(例:関西・九州地方)では、夏場に蒸し暑さを感じやすい傾向もあります。
💭 住んでから気づく「におい問題」
焼き魚や揚げ物の臭いが翌日まで残る
洗面所や浴室に湿気がこもる
ペット臭・タバコ臭が部屋に染み付く
対策 | 内容 |
熱交換型換気(第1種)導入 | 外気を浄化しつつ湿度を調整 |
キッチン換気の強化 | IHコンロでも局所換気が有効 |
室内乾燥機・除湿機の活用 | 梅雨時の湿気対策に有効 |
💡 施主の体験談
「高気密の家に住んで1年、リビングにペットの臭いが残るのが気になりました。換気システムのフィルターを交換したら改善しましたが、メンテナンスコストの重要性を痛感しました。」
3-3. 設計ミスで“息苦しい家”になることも
気密性を高めること自体は良いことですが、設計が不十分だと「息苦しい」と感じる家になることがあります。これは、換気の風量・気流・空気の入れ替わりが適切でないことが原因です。
状況 | 問題点 |
換気計画が不均一 | 一部の部屋だけ空気が滞留する |
給気口・排気口の配置ミス | 部屋ごとの空気の流れが悪い |
内装材の選定ミス | VOC(揮発性有機化合物)の放出で空気汚染 |
特に、VOC(シックハウスの原因物質)を多く含む建材を使用している場合、気密性が高い家ほど空気汚染の影響を受けやすいという paradox(逆効果)が起こります。
⚠️ 注意
高気密=高品質ではありません。設計士・施工業者が気流設計と換気容量を理解していなければ、「性能の数値は優秀なのに、暮らしにくい家」になってしまいます。
3-4. 夏場の熱こもり・電気代上昇リスク
冬は暖かい高気密住宅も、夏には逆効果になるケースがあります。外気を遮断している分、日射熱や家電の排熱がこもりやすいのです。
🔥 よくある事例
夜でも室温が下がらず、寝苦しい
エアコンを常時稼働させる必要がある
屋根断熱が甘く、天井裏が高温に
原因 | 対策 |
南面窓の過剰採光 | 外付けブラインド・庇で日射遮蔽 |
熱気滞留 | サーキュレーターや吹き抜け換気 |
換気経路の不備 | シーリングファンで空気循環を補助 |
🧱 プロの助言
「夏の熱対策は“断熱”よりも“遮熱”と“通風”。気密性を高めた家ほど、設計段階で風の抜け道を意識することが大切です。」
3-5. メンテナンスコスト・トラブルの増加
高気密住宅では、換気設備・フィルター・熱交換機の定期清掃が欠かせません。フィルターが目詰まりすると、空気の流れが悪化し、湿気やカビが発生するリスクが高まります。
項目 | メンテナンス頻度 | 概算費用(年) |
換気フィルター交換 | 3〜6か月ごと | 3,000〜10,000円 |
ダクト清掃 | 2〜3年ごと | 約2〜5万円 |
熱交換器の清掃 | 年1回 | 約1〜3万円 |
💬 専門家コメント
「高気密住宅のメンテナンスは“目に見えない部分”ほど重要です。換気装置を放置すると、快適さが一気に失われます。“性能を維持するための維持費”も計画に入れておくべきです。」
👇もっと深く知りたい方はこちら
🧩 まとめ:デメリットは「設計と運用のバランス」で回避できる
気密性の高さは住宅性能の象徴ですが、その快適さを維持するには「知識」と「管理」が欠かせません。言い換えれば、**デメリットの多くは“構造そのもの”ではなく“設計と運用の問題”**です。
デメリット | 原因 | 対策の方向性 |
結露・カビ | 換気不足 | 熱交換換気+通気層設計 |
におい・湿気 | 通気不良 | 給排気バランス調整 |
息苦しさ | 気流設計の欠如 | 空気の流れを可視化 |
熱こもり | 遮熱不足 | 窓・屋根設計の最適化 |
🧰 プロのアドバイス
「高気密=高性能」と思い込むのではなく、“暮らしやすいバランス”を見つけることが家づくりの本質です。C値・UA値だけでなく、換気システム・通風・日射コントロールも併せて考えましょう。

「気密性の高い家」は、設計・施工・住まい方のどれか一つでも欠けると、性能が逆効果になることがあります。ここでは、実際に起こりやすい3大トラブルを、原因と対策を交えて紹介します。
4-1. 結露による壁内腐食・断熱材の劣化
高気密住宅の代表的なトラブルが「壁内結露」です。これは、目に見えない壁の中で水蒸気が冷やされて水滴になり、木材や断熱材を腐らせてしまう現象です。
🔍 発生メカニズム
冬場、室内の湿った空気が壁内に侵入
外壁付近の温度が低く、水蒸気が結露
木材・断熱材が濡れたまま乾かず、腐食・カビ発生
被害の種類 | 内容 | 影響 |
断熱材の劣化 | グラスウール・セルロースなどが湿気を吸収 | 断熱性能の低下 |
木部腐食 | 構造材が腐る | 建物寿命の短縮 |
カビ発生 | 壁内の黒カビ繁殖 | 健康被害・臭いの原因 |
💡 重要ポイント
高気密住宅は“湿気を閉じ込めやすい”構造。換気だけでなく、防湿層・通気層・断熱層のバランス設計が不可欠です。
✅ 対策チェックリスト
防湿シートの施工精度を確認(隙間・破れNG)
壁内通気層を確保して湿気を逃がす
換気システムの定期メンテナンス
室内加湿器の使いすぎに注意
🧱 専門家のコメント
「結露は“断熱性能の高さ”では防げません。防湿層の設計と施工管理が命です。図面だけでなく、実際の施工現場確認をおすすめします。」
👇もっと深く知りたい方はこちら
4-2. 換気システムの不具合による空気汚染
高気密住宅では、計画換気が正常に動いているかが健康を左右します。換気システムに不具合があると、二酸化炭素やホルムアルデヒドなどの汚染物質が室内に滞留し、シックハウス症候群を引き起こす可能性があります。
トラブル内容 | 原因 | 主な症状 |
換気風量の不足 | フィルター詰まり・ファン劣化 | 酸欠・だるさ・頭痛 |
換気経路の設計ミス | 吸気・排気のバランス不良 | 部屋ごとの空気ムラ |
ダクト内の汚染 | ホコリ・カビ・虫の死骸蓄積 | 臭気・健康リスク |
💬 実際の事例(2024年・愛知県)
新築2年目でLDKの天井裏から異臭。調査の結果、ダクト内に湿気がこもりカビが発生。換気経路の設計が複雑で清掃が困難だったことが原因。
✅ 改善策
定期的な換気風量測定(2〜3年に1回)
フィルター清掃を3か月ごとに実施
熱交換型換気のダクトは「点検口つき」を選ぶ
換気経路をシンプルに設計する
🧰 プロのアドバイス
「“空気が入ってくる道”と“出ていく道”の両方を設計できているかが鍵。換気経路を確認せずに高気密住宅を選ぶのは、呼吸の出口を塞いだ家に住むようなものです。」
4-3. ペット・調理臭が抜けにくい環境
「気密性が高い=臭いが逃げにくい」。これは実際に住んでみて初めて気づく問題です。特に共働き世帯やペット飼育家庭では、生活臭の蓄積が気になるケースが多発しています。
🐾 よくある悩み
ペット臭やトイレ臭が玄関・廊下に残る
揚げ物・焼肉などの油臭が翌日も残る
洗面所や脱衣所のカビ臭が取れない
原因 | 対応策 |
換気経路の偏り | 局所換気扇を増設(トイレ・脱衣所) |
換気フィルターの詰まり | 3か月ごとに清掃 |
臭いの滞留 | アロマディフューザーや24h換気強化 |
👃 施主の声
「新築1年目は快適でしたが、2年目以降に料理臭がこもるようになりました。フィルター清掃を怠っていたことが原因。**“気密は維持管理が命”**だと実感しました。」
💬 専門家コメント
「気密性の高い家では、“換気と消臭の設計”も性能の一部。特にオープンキッチンは、IHでも油煙対策が必要です。」
🧩 まとめ:トラブルの多くは“性能の過信”から起こる
高気密住宅で起こるトラブルのほとんどは、「構造的な欠陥」よりも「運用・理解不足」によるものです。つまり、“高気密=万能”と過信しないことが、トラブル防止の第一歩です。
トラブル種別 | 主因 | 対策の方向性 |
壁内結露 | 通気不足・防湿層不良 | 通気層+換気管理 |
空気汚染 | 換気経路ミス | 設計段階で経路シミュレーション |
臭い残留 | フィルター清掃不足 | メンテナンスの定期化 |
🧱 プロ視点の総括
高気密住宅の“本当の性能”は、完成直後ではなく5年後に現れます。快適さを維持するには、「設計+施工+運用」の3つをトータルで見直す必要があります。

高気密住宅は、断熱性能や省エネ性に優れる一方で、設計バランスを欠くと住み心地が悪化することもあります。そこで重要なのが、「適度な気密」と「正しい換気設計」の両立です。この章では、気密性を高めつつも“息苦しくない家”をつくるための対策を紹介します。
5-1. 第1種換気(熱交換換気)システムの導入
気密性が高い住宅ほど、換気の質が家の快適性を左右します。そのために有効なのが、「第1種換気(全熱交換型)」の採用です。
🔧 第1種換気とは?
給気・排気の両方を機械で制御する方式。冬は外気を暖めて室内に取り込み、夏は冷やして入れるため、室温を一定に保ちながら換気ができます。
換気方式 | 特徴 | メリット | 注意点 |
第1種 (全熱交換型) | 給気・排気とも機械制御 | 温度ロスが少ない・花粉除去 | コスト・清掃頻度が必要 |
第2種 | 給気のみ機械・排気は自然 | 清潔な空間(病院向け) | 家庭用には不向き |
第3種 | 排気のみ機械・給気は自然 | 安価で施工が簡単 | 冬は外気が冷たい |
💬 専門家コメント
「高気密住宅では第1種換気が最適。外気温の影響を最小限に抑えつつ、花粉・PM2.5も除去できるため、健康面でも有利です。」
✅ メンテナンスのポイント
フィルター清掃:3か月ごと
熱交換素子の洗浄:年1回
換気経路の点検:2年ごと
👇もっと深く知りたい方はこちら
5-2. 換気口・吸気経路を定期点検する
どんな高性能換気システムを導入しても、実際に空気が流れていなければ意味がありません。換気口や吸気グリルの詰まり・配置ミスがあると、空気の流れが偏って結露や臭いの原因になります。
🧾 点検チェックリスト
チェック項目 | 内容 | 頻度 |
吸気口の汚れ | ホコリ・虫の詰まりがないか | 月1回 |
排気口の動作 | 空気の吸い込みを手で確認 | 月1回 |
換気フィルター | 掃除または交換 | 3か月ごと |
換気経路 | 冷暖房や家具で塞がれていないか | 随時 |
💡 プロのワンポイント
換気は「入口と出口の両方」が揃って初めて機能します。給気口をふさぐ家具配置やカーテンの干渉も要注意です。
5-3. 適度な開放感を意識した設計
高気密住宅の「息苦しさ」を軽減するには、風や光が抜ける“心理的な開放感”の設計が欠かせません。完全密閉ではなく、“意図的な抜け”をつくることで、体感的な快適性が向上します。
🌿 設計で工夫できるポイント
吹き抜けや勾配天井で空気の循環を促す
室内窓・高窓を設けて視覚的な抜け感を演出
採光設計と通風ラインを両立させる(南北通風・風抜け)
内装色を明るくして心理的閉塞感を軽減
👨💼 建築士の実体験コメント
「C値0.3の超高気密住宅でも、吹き抜け+内窓+熱交換換気を組み合わせれば、閉塞感は感じません。“密閉”ではなく“制御された空気”をデザインすることが重要です。」
5-4. “高気密=高断熱”を前提にしすぎない
気密性を高めると、つい「断熱性も上がる」と考えがちですが、実際は別の性能です。断熱が不十分なまま気密だけを高めると、壁内結露や温度ムラの原因になります。
項目 | 気密性能(C値) | 断熱性能(UA値) |
定義 | 隙間の少なさ | 熱の通しにくさ |
主な目的 | 空気の漏れ防止 | 室温保持・省エネ |
改善手法 | テープ・シート施工 | 断熱材の厚み・材質 |
注意点 | 換気の確保が必要 | 適切な通気層が必要 |
💬 専門家の指摘
「C値だけを競うような“性能マウント”が流行しましたが、実際の快適性は断熱・遮熱・通気・換気のバランスで決まります。数値より“体感”を重視しましょう。」
👇もっと深く知りたい方はこちら
5-5. 暮らし方で気密性を活かす工夫
設計や設備だけでなく、日々の暮らし方も快適性を左右します。どんな高性能住宅でも、間違った使い方をすると性能を発揮できません。
🏠 快適な暮らしのための習慣リスト
24時間換気は常時ONにする(電気代より健康優先)
室内干しは短時間+除湿機を併用
加湿器は50%以下を目安に運転
冬は窓を短時間開けて自然換気をプラス
定期的にフィルター掃除を行う
💡 豆知識
換気を止めてしまうと、たった1日でCO₂濃度が「不快レベル(1,000ppm)」を超えることがあります。家の“呼吸”を止めないことが何よりの快適対策です。
🧩 まとめ:理想は“制御された気密性”
気密性は「高ければ良い」ものではありません。理想的なのは、必要な空気の流れをコントロールできる家。つまり、「閉じすぎず、逃しすぎず」の中庸設計が最も快適です。
対策領域 | 内容 | 効果 |
設計 | 換気経路・開放感の確保 | 息苦しさ軽減 |
設備 | 熱交換換気・フィルター管理 | 空気品質向上 |
住まい方 | 換気を止めない・清掃 | トラブル防止 |
👷♂️ プロのアドバイス
気密性能を競うより、「快適な気候をどう再現できるか」を考えるべきです。技術ではなくバランス感覚が、真の“良い家”をつくります。
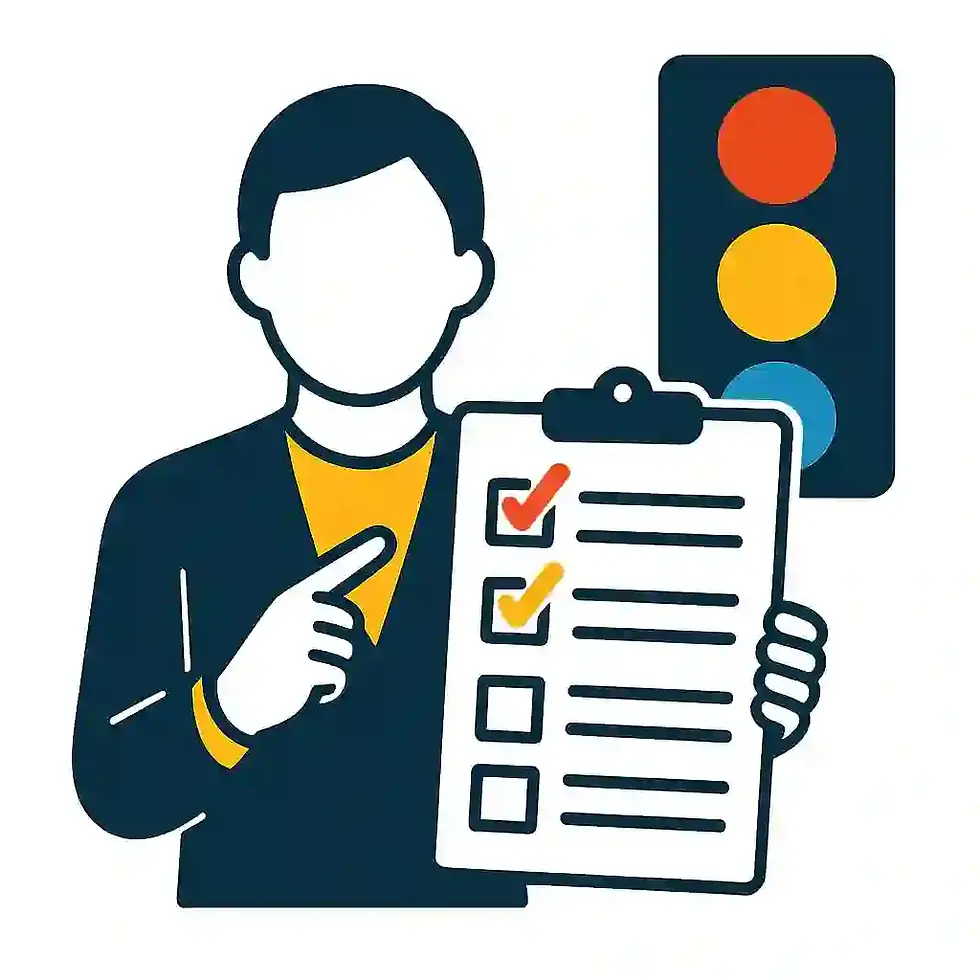
高気密住宅は、正しく理解して建てれば快適で省エネな理想の家になります。しかし、「高性能」をうたうだけの住宅会社も多く、C値・UA値などの数値だけで判断するのは危険です。この章では、契約前に確認すべき重要なポイントを3つの観点から整理します。
6-1. 設計士・工務店の気密測定実績を確認
「高気密」と謳う住宅会社は多いですが、実際に気密測定を実施しているかどうかで信頼性が大きく変わります。
🔍 チェックすべき3つのポイント
項目 | 内容 | 理想値 |
測定実績 | 全棟測定か、サンプル測定か | 全棟実施が望ましい |
C値(相当隙間面積) | 隙間の少なさを示す数値 | 0.5以下が高気密の目安 |
測定者 | 自社社員 or 第三者機関 | 第三者測定が信頼性高い |
💬 専門家の声
「C値0.5未満を出すのは技術的に難しくありませんが、安定して出せる施工品質こそが信頼の証。“1棟限りの実績”ではなく、“平均性能”を確認しましょう。」
✅ 契約前の質問例
気密測定は全棟行っていますか?
C値の測定結果を提示してもらえますか?
測定は第三者機関によるものですか?
6-2. 実際のC値・UA値を数値でチェック
気密性(C値)と断熱性(UA値)は、住宅性能を示す最重要指標です。しかし、これらの数値は地域・建物形状・窓の数などで大きく変わるため、単純比較はできません。
📊 C値・UA値の基準目安
地域 | C値の目安 | UA値の目安 | コメント |
北海道・東北 | 0.3〜0.5 | 0.28以下 | 高断熱住宅が主流 |
関東・中部 | 0.4〜0.7 | 0.46以下 | バランス重視が理想 |
関西・九州 | 0.6〜0.8 | 0.56以下 | 通風設計との併用が重要 |
💡 補足
C値=小さいほど隙間が少なく、UA値=小さいほど熱が逃げにくい。どちらも「低いほど良い」が、数字だけで快適性を保証できるわけではない点に注意。
🧱 プロのアドバイス
「C値0.3でも換気計画が悪ければ息苦しい家に。一方、C値1.0でも風の抜けが良ければ快適に暮らせます。“性能数値+設計の質”で判断するのが正解です。」
メンテナンス費・換気コストも比較する
高気密住宅の性能を維持するには、定期的な点検・清掃・交換コストが必要です。見落とされがちですが、このランニングコストを事前に把握しておくことが後悔防止につながります。
💰 年間維持費の目安
項目 | 頻度 | 費用目安 |
換気フィルター交換 | 年2〜4回 | 約6,000〜15,000円 |
ダクト清掃 | 2〜3年ごと | 約20,000〜50,000円 |
熱交換器点検・清掃 | 年1回 | 約10,000〜30,000円 |
加湿・除湿機器の保守 | 必要に応じて | 約5,000〜10,000円 |
💬 施主の声(実例)
「高気密高断熱の家に住んで3年、思ったより維持費がかかると実感。でも、適切な清掃を怠ると体調に影響することもあり、必要経費だと割り切っています。」
✅ 契約前の確認リスト
フィルターの清掃・交換頻度
メンテナンスコストの目安
換気装置の保証期間
ダクトへの点検口設置の有無
6-4. 使用する建材・内装材のVOC対策を確認
高気密住宅では、建材から出る化学物質が逃げにくいというリスクがあります。国が定めるF☆☆☆☆(フォースター)基準をクリアしているか確認することが大切です。
チェック項目 | 内容 | 重要度 |
使用建材の等級 | F☆☆☆☆(最低限) | ★★★★★ |
接着剤・塗料の成分 | ホルムアルデヒド・トルエンなど | ★★★★☆ |
換気システム | 24時間換気+フィルター除去機能 | ★★★★★ |
💡 アドバイス
「特に子ども部屋や寝室はVOC濃度が上がりやすい。換気を止めず、低VOC建材を選ぶのが鉄則です。」
6-5. 「気密性の高い家」を建てる施工体制を確認
気密性は、設計よりも施工精度に大きく左右されます。どれだけ良い設計でも、職人の施工ミスひとつでC値が悪化することも珍しくありません。
🧱 チェックすべき施工体制
気密処理専門の担当者がいるか
外皮施工(防湿シート・断熱気密テープ)を自社管理しているか
現場ごとのC値実測を実施しているか
現場写真・データを共有してくれるか
👷♂️ 専門家コメント
「気密は“測ること”でしか証明できません。『うちは高気密仕様です』という口約束ではなく、数値と写真で裏付けがある会社を選びましょう。」
🧩 まとめ:数字より「暮らしやすさ」で選ぶこと
気密性の高い家を選ぶとき、C値や性能表だけで判断するのは危険です。快適性は「設計・施工・換気・維持」の4要素が揃ってこそ成立します。
判断基準 | チェック内容 | 重要度 |
性能数値 | C値・UA値の実測 | ★★★★☆ |
設計品質 | 換気計画・風通し | ★★★★★ |
施工品質 | 防湿・通気・断熱の精度 | ★★★★★ |
維持管理 | メンテコスト・清掃性 | ★★★★☆ |
💬 著者コメント
「“高気密住宅”とは、数字を追う家ではなく、家族の健康と暮らしを守る仕組みを整えた家のこと。価格よりも“安心して呼吸できる家”を基準に選んでください。」

高気密住宅は、住宅性能の進化を象徴する存在です。しかし、その「性能」が必ずしも“快適な暮らし”を保証するわけではありません。重要なのは、気密・断熱・換気・通気・設計のすべてがバランスよく機能していることです。
7-1. 「気密性が高い家」は“呼吸の設計”が必要
気密性を高めることは、家の「呼吸のコントロール」を意味します。つまり、空気の出入りを“制御下”に置くということ。しかし、制御が不十分だと、結露・カビ・臭い・体調不良といった弊害が生じます。
💡 正しい考え方
高気密住宅=空気を閉じ込める家、ではない
高気密住宅=空気の流れを「設計」する家
“閉める”より“整える”が理想
🧱 専門家の言葉
「高気密住宅の本質は“密閉”ではなく“制御”。設計段階で空気の通り道をデザインできているかが、性能の分かれ目です。」
7-2. 性能を“目的化”しないことが大切
C値やUA値などの数値は、あくまで「結果」を示す指標です。これらを“目的”にしてしまうと、暮らしに必要な柔軟性を失いがちです。
視点 | 性能偏重の家 | バランス型の家 |
目的 | 数値の達成 | 住みやすさ・健康維持 |
設計 | 機械的・均質化 | 生活動線・光・風を重視 |
メンテナンス | 複雑でコスト高 | シンプルで継続しやすい |
満足度 | 初期は高いが低下しやすい | 長期的に安定 |
💬 建築士コメント
「“性能を上げる=快適”ではなく、“性能を活かせる暮らし”を設計することが重要。家は数値ではなく、住む人の体感で評価されるべきです。」
7-3. 「高気密」にすべき家と、そうでない家
すべての家に高気密性能が必要なわけではありません。地域・家族構成・生活習慣によって、最適なレベルは異なります。
家のタイプ | 向いている気密レベル | 理由 |
寒冷地(北海道・東北) | C値0.3〜0.5 | 暖房効率・防露性能が重要 |
温暖地(関東・関西) | C値0.5〜0.8 | 通風と冷房の両立が必要 |
沿岸部・高湿度地域 | C値0.6〜1.0 | 結露対策と通気性のバランス |
高齢者中心の家庭 | C値0.5〜0.7 | 健康と温度安定性重視 |
💡 ワンポイント
“性能の高さ”よりも、“自分の地域と暮らしに合った性能”を選ぶことが、後悔しない家づくりの第一歩です。
7-4. 高気密住宅の「落とし穴」を避ける3原則
これまでの章で紹介した内容をもとに、後悔しないための3原則をまとめます。
🧩 後悔しない3原則
換気設計を軽視しない → 給気・排気・風量バランスを最優先
防湿・断熱・通気の3層設計を守る → 壁内結露と断熱劣化を防ぐ
“施工精度”と“測定データ”で判断する → 広告の言葉ではなく、実測値を確認
👷♂️ 専門家コメント
「高気密住宅で失敗する人の多くは、“知識ではなく感覚”で選んでいます。図面・施工・測定・運用の4段階すべてを理解している会社を選ぶのが安全です。」
7-5. 著者からのメッセージ|“性能”より“暮らし”
筆者は元住宅営業として、多くの「高気密・高断熱住宅」の現場に立ち会ってきました。その中で痛感したのは、「性能だけで幸せになれる家は存在しない」ということです。
🏡 著者コメント
「快適さは“数値”ではなく、“住んでからの満足感”で決まります。たとえば、家族の会話が増えた、朝起きるのが心地よくなった――そう感じられる家こそ、本当の意味で“高性能住宅”です。」
🧾 まとめ表|この記事の要点ダイジェスト
カテゴリー | 要点 | 対応策 |
気密性の意味 | 隙間を減らして外気を遮断 | “閉じる”より“整える” |
主なデメリット | 結露・臭い・換気不良 | 設計・施工・運用の三位一体対策 |
確認すべき数値 | C値・UA値 | 数字だけでなく体感重視 |
施工会社選び | 測定実績・施工精度 | 写真・データ開示の確認 |
暮らし方 | 換気を止めない・清掃を習慣化 | 快適性と健康を両立 |
✅ 最終結論:「高気密=悪」でも「完璧=正解」でもない
高気密住宅は、正しく理解して建てれば人生を豊かにする家になります。一方で、設計・施工・暮らし方を誤れば、健康や快適性を損なうリスクも。
つまり――
気密性とは「目的」ではなく、“快適さをコントロールする手段”である。
この視点を持てば、あなたの家は「性能のための家」から 、「人のための家」へと進化します。
国立研究開発法人 建築研究所(2023):「住宅の断熱・気密施工技術ガイドライン」
— 高気密施工の手順、結露防止設計、換気計画の基本設計を解説。
消費者庁(2024):「高性能住宅に関するトラブル事例集」
— 高気密住宅で実際に起きた換気・結露・シックハウスの苦情事例を紹介。
一般財団法人 日本建築センター(2024):「建築物のエネルギー消費性能基準」
— ZEH・高性能住宅の基準に関する一次情報。
一般社団法人 住宅性能評価・表示協会(2025):「性能表示制度における気密性能評価指針」
https://www.hyoukakyoukai.or.jp/
— C値評価・測定方法の技術解説を含む最新版レポート。
一般社団法人 日本サステナブル建築協会(2024):「省エネ住宅市場動向レポート」
— 高気密・高断熱住宅の普及状況と地域差のデータを掲載。
一般社団法人 日本建材・住宅設備産業協会(2024):「断熱材・気密施工部材の品質ガイド」
— 断熱材・気密テープ・防湿シートなどの選定基準を提示。
一般社団法人 日本住宅性能評価機構(JIO)(2024):「気密測定と施工管理の重要性」
— 高気密住宅の実測データと品質管理体制に関する報告書。
住宅産業新聞社(2025):「高気密住宅における換気システム不具合に関する報道特集」
— 業界トレンド・施工不良による被害報告を掲載。
近藤典子(2023)『健康を守る高気密住宅の換気設計』オーム社.
— 住宅内空気の流れと結露対策の実践的手法を解説。
西方里見(2024)『パッシブデザインのすべて』エクスナレッジ.
— 高断熱・高気密住宅を“快適性”で評価するための理論書。
吉田登(2024)『ZEH住宅の真実:エネルギー効率と暮らしやすさの両立』日経BP.
— 実測データをもとに性能と健康・コストの関係を考察。
-26.webp)

-39-2.webp)


