注文住宅のローンはいつから支払い開始?契約から引き渡しまで徹底解説
- 見積もりバンク担当者

- 2025年5月7日
- 読了時間: 16分
更新日:2025年12月25日
更新日:2025年12月25日
「注文住宅のローンはいつから支払いが始まるの?」——これは家づくりを検討する多くの人が抱く疑問です。建売住宅とは異なり、注文住宅では「契約・着工・中間金・竣工・引き渡し」と複数のステップを経て資金が動くため、支払い開始のタイミングを誤解すると家計が大きく圧迫されることもあります。
本記事では、契約から引き渡しまでの流れ・住宅ローンの支払い開始時期・つなぎ融資の仕組み・家計への影響を、実務経験を踏まえて徹底解説します。さらに「返済開始を遅らせる方法」や「審査に通りやすいタイミング」など、専門的なアドバイスも交えています。

目次
1-1: この記事でわかること・検索意図の整理
1-2: 注文住宅と建売住宅のローン開始時期の違い
2-1: 注文住宅の資金計画とSTEPごとの流れ
2-2: 土地購入から建物完成までのローンの動き
2-3: ローン支払い開始日(初回返済日)はいつ?
2-4: 支払い開始を遅らせる方法はある?
3-1: 契約の種類とポイント|売買契約・請負契約の違い
3-2: 住宅ローン申込みから本審査までの流れ
3-3: 必要書類と金融機関への提出タイミング
3-4: 引き渡しまでの全体スケジュール例
4-1: つなぎ融資の仕組み・注文住宅で発生する理由
4-2: 家賃と住宅ローンが二重で発生する場合の負担と対策
4-3: つなぎ融資利用時の注意点|メリット・デメリット
5-1: 注文住宅ローンの返済額シミュレーション
5-2: 返済開始時期別の家計負担イメージ
5-3: 諸費用・金利・税金等の注意ポイント
6-1: 「ローン審査はいつ?」「審査に必要な書類は?」
6-2: 「返済期間・返済日に関する疑問」
6-3: 「転職直後は住宅ローンは通る?」「立て続けはNG?」
6-4: 「つなぎ融資が不要なケースとは?」
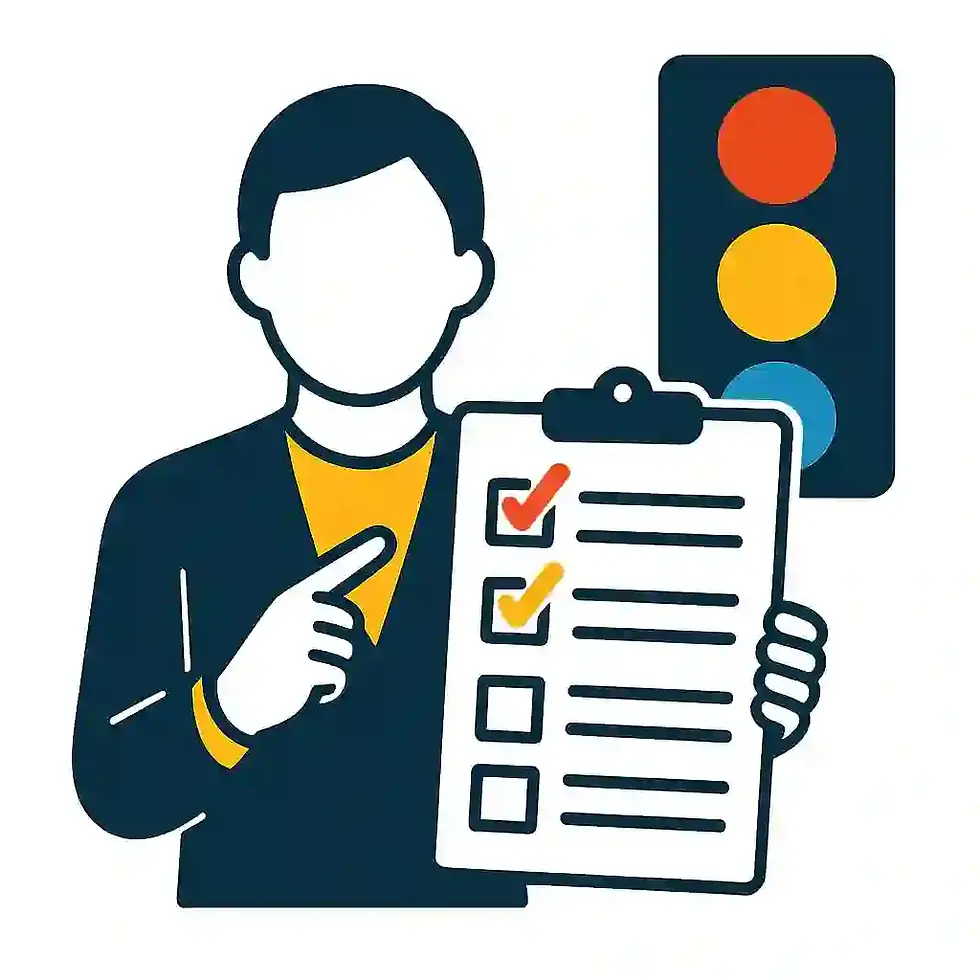
1-1: この記事でわかること・検索意図の整理
注文住宅の住宅ローンは、建売住宅と違い「工事が進むごとに資金が必要」という特徴があります。
読者の検索意図は大きく分けると以下の3つです。
✅ ローンの支払い開始はいつからか知りたい
✅ 契約から引き渡しまでの流れを理解したい
✅ 家賃やつなぎ融資など、二重払いの不安を解消したい
つまり本記事は、**「いつから住宅ローンの返済が始まり、家計にどう影響するのか」**という疑問を解決するための実用的な解説です。
1-2: 注文住宅と建売住宅のローン開始時期の違い
建売住宅の場合、引き渡し時点でローン実行・支払い開始となります。シンプルでわかりやすいのが特徴です。
一方、注文住宅は以下のように複雑です。
📊 比較表:注文住宅と建売住宅のローン開始時期
住宅タイプ | ローン実行のタイミング | 支払い開始 | 特徴 |
建売住宅 | 引き渡し時 | 翌月 or 翌々月 | シンプル・二重払いなし |
注文住宅 | 契約・着工・中間金・竣工ごと | 金融機関による | つなぎ融資・二重払いリスクあり |
💡 プロ視点のアドバイス
実務では「つなぎ融資」の有無で返済開始のタイミングが変わります。金融機関や工務店の資金要求スケジュールを事前に確認しておくことが、家計の安定につながります。
👇 あわせて読みたい関連記事

2-1: 注文住宅の資金計画とSTEPごとの流れ
注文住宅のローン開始時期を理解するには、まず「資金がどのタイミングで必要になるのか」を押さえることが重要です。
注文住宅は建売と違って「契約~着工~上棟~完成~引渡し」と段階を踏むため、それぞれの工程で支払いが発生します。
📊 注文住宅の資金フロー例(一般的なケース)
工程 | 支払い内容 | 資金の出どころ | タイミング |
土地購入 | 土地代金(売買契約) | 住宅ローン(土地先行融資 or つなぎ融資) | 契約直後 |
建物契約 | 契約金(請負契約金の一部、5〜10%) | 自己資金 or つなぎ融資 | 請負契約締結時 |
着工時 | 着工金(工事費用の30%前後) | つなぎ融資 | 着工直前 |
上棟時 | 中間金(工事費用の30〜40%) | つなぎ融資 | 上棟後 |
竣工時 | 残代金(工事費用の残り) | 住宅ローン実行 | 完成・引渡し時 |
このように注文住宅では、**「引渡し前に支払いが複数回発生する」**のが特徴です。
💡 プロ視点のアドバイス
実際の現場では「金融機関によっては土地と建物を同時にローン実行できない」ことが多く、つなぎ融資が必要になります。特に地方銀行や信用金庫ではこの仕組みが一般的です。
👇 あわせて読みたい関連記事
2-2: 土地購入から建物完成までのローンの動き
ここでは土地付き注文住宅(最も多いケース)を想定し、資金の流れを時系列で整理します。
📌 時系列の流れ
土地購入
先に土地を契約し、決済が必要になる。
この時点で「土地先行融資」または「つなぎ融資」を利用。
建物契約(請負契約)
工務店やハウスメーカーと建築請負契約を結び、契約金(手付金)を支払う。
建築開始(着工金支払い)
基礎工事が始まる前に着工金を支払う。
金額は建物本体価格の30%前後。
上棟(中間金支払い)
骨組みが完成した段階で支払い。
金額は建物本体価格の30〜40%。
竣工・引渡し(残金支払い)
工事が完了し、建物の登記を行った後に残代金を支払う。
このタイミングで住宅ローンが正式に実行される。
2-3: ローン支払い開始日(初回返済日)はいつ?
金融機関ごとに異なりますが、多くは「ローン実行日の翌月または翌々月」が初回返済日になります。
例)3月25日にローン実行 → 初回返済は4月27日または5月27日
📌 注意点
土地先行融資を使った場合 → 土地購入時点から利息負担が発生
つなぎ融資を使った場合 → 工事中も利息が発生し、引渡しまで支払いが続く
引渡し後 → 本格的に住宅ローン返済がスタート
2-4: 支払い開始を遅らせる方法はある?
「できれば引渡し後まで支払いを始めたくない」という声は多いです。そこで使えるのが以下の方法です。
✅ 支払い開始を遅らせる工夫
金融機関に「元金据置型ローン」を選ぶ(一定期間は利息のみ支払い)
自己資金を多めに準備し、つなぎ融資を最小限にする
返済開始日を調整できる金融機関を選ぶ
建築スケジュールを家賃契約の更新時期と合わせる
ただし、利息負担が増える可能性があるため、安易に遅らせるのではなく「家計全体の収支シミュレーション」を行うことが必須です。
💬 実体験談(30代・広島県のご夫婦)
「私たちは土地購入から引渡しまで約10か月ありました。その間、家賃+つなぎ融資の利息を支払い続ける必要があり、かなり負担を感じました。最初に銀行や工務店に資金スケジュールを確認しておけば、もっと計画的に進められたと思います。」

3-1: 契約の種類とポイント|売買契約・請負契約の違い
注文住宅では「土地」と「建物」で契約の種類が異なります。
📌 契約の種類
契約の対象 | 契約の種類 | 主な内容 | 注意点 |
土地 | 売買契約 | 土地代金・決済日・所有権移転 | ローン実行時期と連動する |
建物 | 請負契約 | 工事費用・工期・支払い条件 | 着工金・中間金・完成金の分割支払い |
👉 注文住宅では「土地購入が先・建物は後」という流れが多いため、二重で資金が必要になるのが特徴です。
💡 プロ視点のアドバイス
契約の段階で支払い条件をよく確認しましょう。特に工務店によっては「着工時50%」など大きな金額を要求されるケースもあり、資金繰りに直結します。
👇もっと深く知りたい方はこちら
3-2: 住宅ローン申込みから本審査までの流れ
住宅ローンは「事前審査(仮審査)」と「本審査」の2段階があります。
📌 住宅ローン申込みの流れ
仮審査(事前審査)
勤務先・年収・借入状況などをもとに融資可能かどうかの一次判定
通常3日〜1週間程度で結果が出る
本審査
提出書類(売買契約書・請負契約書・登記事項証明書など)をもとに金融機関が詳細チェック
1〜3週間程度かかる
金銭消費貸借契約(金消契約)
銀行との正式な契約
これを終えて初めて「融資実行」が可能になる
3-3: 必要書類と金融機関への提出タイミング
住宅ローンの審査には、多くの書類が必要です。
📋 住宅ローンに必要な主な書類
本人関連
身分証明書(運転免許証・パスポートなど)
住民票・印鑑証明書
健康保険証
所得証明(源泉徴収票 or 確定申告書)
土地関連
売買契約書
登記事項証明書
公図・測量図
建物関連
建築請負契約書
建築確認済証
見積書・設計図面
その他
納税証明書
他のローン残高証明
📌 提出タイミングの注意
仮審査 → 本人情報中心
本審査 → 契約書類(売買契約書・請負契約書)が必須
融資実行 → 登記関連の書類が揃った段階で提出
💡 プロ視点のアドバイス
審査の遅延で工事が進まないケースもあります。特に確定申告をしている自営業の方は書類が複雑になりやすいので、早めの準備が必要です。
3-4: 引き渡しまでの全体スケジュール例
ここでは、土地契約から引渡しまでの一般的なスケジュールを示します。
📊 注文住宅のスケジュール例(約10〜12か月)
月数 | 工程 | 主な支払い・手続き |
1か月目 | 土地探し・売買契約 | 手付金・仮審査申込み |
2か月目 | 建物の請負契約 | 契約金支払い・本審査申込み |
3〜4か月目 | 設計打合せ・建築確認申請 | つなぎ融資準備 |
5か月目 | 着工 | 着工金支払い |
6〜7か月目 | 上棟 | 中間金支払い |
9〜10か月目 | 竣工・内覧 | 融資実行・残金支払い |
10〜12か月目 | 引渡し・入居 | 住宅ローン返済開始 |
💬 実体験談(40代・東京都のご夫婦)
「本審査の承認が下りるのに1か月以上かかり、工務店とのスケジュール調整が大変でした。銀行によってスピード感が全く違うので、複数行に同時申込みしておけばよかったと思います。
👇 あわせて読みたい関連記事

4-1: つなぎ融資の仕組み・注文住宅で発生する理由
注文住宅では「建物完成後」に住宅ローンが実行されるのが一般的です。しかし実際には、土地購入・着工金・中間金などの段階でまとまったお金が必要になります。
この「完成前に必要なお金」をつなぐために使うのが つなぎ融資 です。
📌 つなぎ融資の流れ(例)
土地購入 → つなぎ融資を利用
着工時 → 着工金をつなぎ融資から支払う
上棟時 → 中間金をつなぎ融資から支払う
竣工・引渡し → 住宅ローンが実行され、つなぎ融資を一括返済
💡 なぜ必要?
住宅ローンは「完成した建物」が担保
工事途中では担保にならないため、銀行は融資できない
そこで工事中の資金を「つなぎ」で借りる仕組みが必要になる
👇 あわせて読みたい関連記事
4-2: 家賃と住宅ローンが二重で発生する場合の負担と対策
注文住宅を建てる人が最も不安に感じるのが、**「家賃+つなぎ融資利息の二重払い」**です。
例)
家賃:8万円
つなぎ融資利息:2万円
→ 合計10万円を工事期間中に支払うことに
完成までに8〜12か月かかれば、その分だけ負担が増えます。
📊 家賃+つなぎ融資のシミュレーション
工事期間 | 家賃(月8万円) | つなぎ融資利息(月2万円) | 合計 |
6か月 | 48万円 | 12万円 | 60万円 |
9か月 | 72万円 | 18万円 | 90万円 |
12か月 | 96万円 | 24万円 | 120万円 |
✅ 二重払いを軽減する工夫
建築スケジュールを最短化(契約から引渡しまでを8か月以内に収める)
実家に仮住まいする(工事期間中の家賃を抑える)
銀行によっては「土地先行融資」制度を利用し、つなぎ融資を避けられるケースもある
💡 実体験談(30代・大阪府のご夫婦)
「私たちはつなぎ融資で毎月2万円の利息が発生し、家賃と合わせて12万円近い負担になりました。最初に資金計画をもっと細かく確認しておけば、余裕を持って準備できたと思います。」
4-3: つなぎ融資利用時の注意点|メリット・デメリット
つなぎ融資は便利ですが、メリットとデメリットを理解しておかないと後悔につながります。
📌 つなぎ融資のメリット
完成前の支払いに対応できる
自己資金が少なくても家づくりが進められる
工務店や銀行の手続きがスムーズに進みやすい
📌 つなぎ融資のデメリット
金利が高い(住宅ローンより1〜2%高い場合が多い)
完済まで元金は減らず、利息のみの支払い
融資ごとに手数料がかかる(数万円程度/回)
📊 比較表:住宅ローンとつなぎ融資
項目 | 住宅ローン | つなぎ融資 |
金利 | 0.3〜1.0%程度 | 2〜3%程度 |
担保 | 完成した建物 | なし(信用による) |
返済 | 元利均等返済 | 利息のみ |
実行タイミング | 引渡し時 | 工事途中 |
💡 プロ視点のアドバイス
「つなぎ融資を利用せざるを得ない」ケースは多いですが、銀行によっては土地と建物を一括で先行融資してくれる制度もあります。複数の金融機関を比較することで数十万円単位で差が出るため、早めの情報収集が欠かせません。
👇もっと深く知りたい方はこちら

5-1: 注文住宅ローンの返済額シミュレーション
住宅ローンの返済額は、借入額・金利・返済期間によって大きく変わります。ここでは、注文住宅でよくある「建物3,000万円+土地1,500万円=合計4,500万円」を借りるケースを想定してシミュレーションしてみます。
📊 住宅ローン返済シミュレーション(例)
借入額 | 金利 | 返済期間 | 月々返済額 | 総返済額 |
4,500万円 | 0.5% | 35年 | 約115,000円 | 約4,830万円 |
4,500万円 | 1.0% | 35年 | 約128,000円 | 約5,370万円 |
4,500万円 | 1.5% | 35年 | 約142,000円 | 約5,940万円 |
👉 金利が1%上がるだけで月々約27,000円・総額1,100万円以上の差になります。
💡 プロ視点のアドバイス
実務では「土地先行融資」や「つなぎ融資」を併用することも多く、引渡し前の利息負担も加わります。ローン本体だけでなく、工事期間中のコストを含めたトータル資金計画が必要です。
👇 あわせて読みたい関連記事
5-2: 返済開始時期別の家計負担イメージ
注文住宅の場合、返済開始時期は大きく2パターンに分かれます。
📌 返済開始のタイミング別シミュレーション(借入額4,500万円/金利1.0%/35年)
返済開始時期 | 初回返済額 | 工事中の負担 | 家計への影響 |
引渡し後(一般的) | 128,000円/月 | 家賃+つなぎ融資利息(10〜12万円/月) | 工事期間中は二重払いが発生 |
土地購入時から | 128,000円/月 | 住宅ローン返済がすぐ始まる | 家賃を払わない人には有利 |
元金据置型を利用 | 数万円(利息のみ) | 工事中の負担軽減 | ただし引渡し後の返済額が増える |
💡 実体験談(広島県・30代男性)
「私の場合、土地購入後すぐに返済が始まりました。家賃も支払っていたため、半年ほどは二重払い状態に。最初に資金計画をもっと精密に立てておけば、自己資金を充てて負担を軽くできたと思います。」
👇 あわせて読みたい関連記事
5-3: 諸費用・金利・税金等の注意ポイント
住宅ローン返済は「本体費用」だけではありません。以下のような諸費用・税金も発生します。
📋 注文住宅で発生する主な諸費用
ローン関連
事務手数料(数万円〜数十万円)
保証料(借入額の2%前後 or 金利上乗せ型)
印紙税(契約書ごとに1〜2万円程度)
登記関連
登録免許税
司法書士報酬
税金・保険
固定資産税(建物完成後から発生)
火災保険・地震保険(引渡し時に一括支払いが多い)
📊 諸費用の目安
項目 | 金額目安 |
ローン手数料 | 3〜33万円 |
保証料 | 80〜100万円(4,000万円借入時) |
登記費用 | 20〜50万円 |
火災保険 | 20〜40万円(10年一括) |
その他(引越し費用など) | 20〜50万円 |
合計 | 150〜250万円程度 |
💡 プロ視点のアドバイス
特に「保証料」と「火災保険料」は銀行やプランによって大きく差があります。最近はネット銀行で「保証料0円」の商品も増えていますが、工務店や不動産会社と提携している地銀では逆に高めに設定されていることもあります。必ず複数行を比較しましょう。
👇もっと深く知りたい方はこちら

6-1: 「ローン審査はいつ?」「審査に必要な書類は?」
Q:住宅ローン審査はいつ受ければいいですか? A:土地や建物の契約前に「仮審査」を行い、契約後すぐに「本審査」に進むのが基本です。
仮審査(事前審査)
タイミング:土地契約・建物契約の前
内容:年収・勤務先・借入状況を中心に簡易的な審査
期間:数日〜1週間程度
本審査
タイミング:土地・建物の契約後
内容:契約書類・登記関係の確認、信用情報の詳細チェック
期間:1〜3週間程度
📋 必要書類の代表例
身分証明書(運転免許証など)
住民票・印鑑証明書
所得証明(源泉徴収票 or 確定申告書)
売買契約書(土地)・請負契約書(建物)
建築確認済証
💡 プロ視点
本審査の承認が出ないと工事が進められないため、工務店の工程とズレが出ないように早めの準備が鉄則です。
6-2: 「返済期間・返済日に関する疑問」
Q:返済期間は何年にするのがベスト? A:一般的には35年返済を選ぶ人が多いですが、ライフプランに応じて短縮返済も検討しましょう。
35年返済 → 月々の負担を軽くできる
25年返済 → 総返済額を減らせる
繰上返済 → 家計に余裕が出た時に元金を減らせる
Q:返済日は指定できますか? A:ほとんどの銀行で「毎月◯日」と指定可能。給料日の後を選ぶのが安心です。
6-3: 「転職直後は住宅ローンは通る?」「立て続けはNG?」
Q:転職したばかりでも住宅ローンは組めますか? A:厳しい場合が多いです。特に1年未満の転職直後は審査が不利になります。
銀行は「安定した収入」を重視
勤続年数3年以上が望ましいが、1年以上あれば柔軟に対応してくれる金融機関もある
公務員や大手企業への転職なら有利に働くこともある
Q:転職や借入を立て続けにするとNG? A:はい。車のローンやカードローンの新規借入直後はマイナス評価になりやすいです。住宅ローン審査前の大きな借入は避けましょう。
6-4: 「つなぎ融資が不要なケースとは?」
Q:必ずつなぎ融資を利用しないといけないの? A:いいえ。条件によっては不要なケースもあります。
✅ つなぎ融資が不要になるケース
自己資金が多く、着工金や中間金を現金で支払える場合
銀行が「土地+建物一括融資」に対応している場合
完成済みの建売住宅を購入する場合
💡 プロ視点
最近は「つなぎ融資不要」をアピールする銀行も増えています。ただし、金利や手数料が割高なケースもあるので「本当にお得か」を必ず試算しましょう。
📌 まとめチェックリスト(Q&A編)
審査は「仮審査 → 本審査」の順で進める
契約後すぐに本審査が必要になる
返済日は給料日の後に設定する
転職・借入直後は審査が厳しい
自己資金次第でつなぎ融資を回避できる

✅ 本記事のまとめポイント
注文住宅のローンはいつから?
→ 基本は「建物完成・引渡し後」から本格返済が始まるが、土地購入時や着工時点から利息負担が発生するケースもある。
建売との違い
→ 建売は「引渡し時に一括実行」なのでシンプル。注文住宅は「段階ごとに資金が必要」で複雑。
つなぎ融資の注意点
→ 工事中の資金をカバーできるが、利息や手数料がかかり家賃との二重負担リスクあり。
家計への影響
→ 返済開始時期を誤解すると家賃・利息の二重払いで数十万円単位の差が出る。必ずシミュレーションが必要。
審査・融資実行のタイミング
→ 仮審査は契約前、本審査は契約後。転職や借入直後は不利になるため注意。
📋 最後に読者へのアドバイス
資金計画は必ず「土地・建物・諸費用・工事期間中の利息」まで含める
工務店や銀行任せにせず、自分で資金フローを把握すること
複数の金融機関を比較し、つなぎ融資の有無・条件を確認すること
💬 プロの一言
注文住宅の資金繰りは「情報を持っている人ほど得をする」仕組みになっています。営業マンの言葉を鵜呑みにせず、必ず第三者の視点で「本当に必要な費用」と「返済開始のタイミング」を確認してください。
🧑💼 専門家コメント
「契約前にローン審査のスケジュールを把握しておくと、工務店とのやり取りがスムーズになります。」
「利息負担を抑えるためには、つなぎ融資の回数を最小限に抑える工夫が必要です。」
「家賃と二重払いになる期間を短縮できるかどうかが、実際の家計インパクトを左右します。」
「シミュレーションを“ローン返済だけ”で終わらせず、固定資産税・保険・維持費まで含めるのが理想です。」
-26.webp)

-39-2.webp)


