固定資産税はいくら?一戸建てとマンションの違いを徹底解説|シミュレーション付き
- 見積もりバンク担当者

- 2025年8月11日
- 読了時間: 16分
更新日:2025年10月7日
更新日:2025年09月26日
マイホームを購入すると必ず発生するのが固定資産税。しかし「実際に毎年どれくらい支払うのか分からない…」と不安に思う方は多いのではないでしょうか。特に戸建てとマンションでは評価額や土地の有無によって負担額が変わるため、事前に 固定資産税 いくら かかるのかを把握しておくことが大切です。
本記事では、固定資産税の計算方法や評価額の仕組みをわかりやすく解説し、戸建てとマンションそれぞれの税額の目安を比較。さらに、減税制度や節税のポイントについても紹介します。これを読むことで、購入後のランニングコストを具体的にイメージでき、安心して資金計画を立てられる知識 が身につきます。
目次
2-1: 固定資産税とは何か?
2-2: 固定資産税の課税対象と評価額の理解
2-3: 固定資産税の仕組みと計算方法
3-1: 一戸建ての固定資産税の平均額
3-2: マンションの固定資産税の平均額
3-3: 一戸建てとマンションの税率の違い
4-1: 評価額からの固定資産税の計算式
4-2: 固定資産税のシミュレーションツールの活用法
4-3: 年ごとの変動に注意するべきポイント
5-1: 固定資産税の軽減措置の種類
5-2: 特例措置の適用条件と申請方法
5-3: 負担軽減に向けた最新情報
6-1: 古い家の固定資産税はいくらか?
6-2: 新築住宅の固定資産税の特徴
6-3: 経年による評価額の変動とは?
7-1: 納税通知書の確認ポイント
7-2: 各種納付方法のメリット・デメリット
7-3: 期限の重要性と支払い時期の確認
8-1: 理解しておくべき固定資産税の基礎知識
8-2: 一戸建て、マンションの税負担を見直す
8-3: 将来の計画に向けた影響を考える

1: 固定資産税シミュレーション(戸建て・マンション対応)
2: 固定資産税はいくら?基礎知識の紹介

2-1: 固定資産税とは何か?
固定資産税とは、毎年1月1日時点で土地や家屋・償却資産を所有している人に課される市区町村の税金です。この税金は「家を持てば必ずかかる維持コスト」の代表格。地方自治体の大きな収入源であり、住民サービスやインフラ維持に使われています。
【専門家コメント】
「固定資産税は“持ち家にかかる唯一のランニングコスト”とも言えます。賃貸とのコスト比較でも見逃せません」(税理士・不動産コンサルタント)
2-2: 固定資産税の課税対象と評価額の理解
課税対象は…
土地
家屋(住宅・マンション含む)
償却資産(事業用設備や機械など)
特に住宅(戸建・マンション)は“家屋+土地”の合計評価額が課税のベースになります。この評価額は3年に1度見直しされ、市町村が「固定資産評価基準」に基づき算定。
【ヒント】
2025年現在、都心部の新築戸建で家屋評価額は2,000万~3,000万円、土地評価額は2,000万~1億円と幅広い。マンションの場合は“共用部を按分”した評価額となる。
\➡ 関連記事:マイホームの年間維持費はどれくらいか?
2-3: 固定資産税の仕組みと計算方法
■ 固定資産税の基本的な計算式
固定資産税額=課税標準額 × 税率(1.4%・標準)土地や家屋の**課税標準額(評価額)**は、市町村が「固定資産評価基準」に従って評価。一般的な税率は1.4%ですが、都市計画税(0.3%など)が加算される場合も。
項目 | 例(戸建) | 例(マンション) |
家屋評価額 | 2,500万円 | 1,500万円 |
土地評価額 | 3,000万円 | 1,000万円(持分) |
合計評価額 | 5,500万円 | 2,500万円 |
固定資産税額 | 77万円 | 35万円 |
都市計画税加算 | +9万円 | +4万円 |
【実体験】
「郊外の新築一戸建ては1年目が約13万円、23区のマンションは初年度約16万円でした。年による評価額の変動や軽減措置の影響も大きいです」
3: 一戸建てとマンションの固定資産税の違い

3-1: 一戸建ての固定資産税の平均額
一戸建て住宅の固定資産税は、建物(家屋)+土地それぞれの評価額を基準に課税されます。評価額はエリア・広さ・築年数によって大きく変動しますが、全国平均で年間12万円〜18万円前後が一般的な水準です。
地域 | 延床面積 | 土地面積 | 合計評価額 | 年間固定資産税 (目安) |
首都圏郊外 | 110㎡ | 150㎡ | 2,800万円 | 約15万円 |
地方都市 | 100㎡ | 120㎡ | 1,800万円 | 約9万円 |
都心部 | 120㎡ | 60㎡ | 4,500万円 | 約22万円 |
【実体験】
「新築戸建(大阪・土地100㎡・建物90㎡)で初年度約11万円。経年で徐々に減っていき、築15年時点では約7万円に下がりました」(40代会社員・購入者)
\➡ 関連記事:住宅メンテナンス費用を抑えるための賢い選び方
3-2: マンションの固定資産税の平均額
マンションは「建物全体の評価額」を専有面積割合で按分し、さらに土地評価額も共有持分として計算されます。新築ファミリータイプ(70㎡前後)で年間8万円〜15万円程度が目安です。
地域 | 専有面積 | 土地持分 | 合計評価額 | 年間固定資産税 (目安) |
都心高層 | 70㎡ | 6㎡ | 2,800万円 | 約13万円 |
郊外大型 | 80㎡ | 20㎡ | 2,000万円 | 約9万円 |
地方中堅 | 65㎡ | 12㎡ | 1,400万円 | 約7万円 |
【実体験】
「横浜市の新築マンション(75㎡)で初年度約12万円。共用部の大規模修繕後は評価額がやや上がることもありました」
3-3: 一戸建てとマンションの税率の違い
基本的に税率はどちらも1.4%(標準)
土地・家屋・マンション全て同じ固定資産税率が適用
ただし都市計画税(0.3%)が追加される地域も
マンションは「共用部の減価償却が反映されやすく、築年数による下落がやや早い」傾向
新築戸建は「土地評価が高いと初年度の負担が大きい」が、軽減措置の適用期間後は評価額が減りやすい
比較項目 | 一戸建て | マンション |
課税対象 | 建物+土地 | 建物(持分)+土地(持分) |
評価額変動 | 経年劣化で大きく下落 | 共用部の減価償却も反映 |
税率 | 原則1.4% | 原則1.4% |
都市計画税 | あり(0.3%等) | あり(0.3%等) |
軽減特例 | 新築住宅特例など | 新築住宅特例など |
【プロ視点コメント】
「実は“新築マンションの方が初年度の固定資産税は高く出る”ケースも増えています。これは建物の評価が高くなりがちな上、土地の按分評価も都市部だと高額なため。逆に、築20年以上になると一戸建てのほうが“課税額の下がり幅が大きい”ため、長期的には持家戸建ての方が税コスパが良い例も多いです」
\➡ 関連記事:土地探し成功のカギは〇〇!意外なポイントとは
4: 固定資産税の計算方法とシミュレーション

4-1: 評価額からの固定資産税の計算式
固定資産税の金額は**「課税標準額 × 税率(通常1.4%)」**で計算されます。課税標準額とは、自治体が定める「固定資産評価基準」により評価された金額であり、土地や家屋ごとに3年ごとに評価替えが行われます(2025年は評価替え年)。
▼ 固定資産税の計算例
物件タイプ | 評価額 (家屋) | 評価額 (土地) | 合計評価額 | 固定資産税額 | 都市計画税 (0.3%) | 年間納付額 |
新築戸建(郊外) | 1,600万円 | 2,000万円 | 3,600万円 | 50.4万円 | 10.8万円 | 61.2万円 |
中古マンション | 800万円 | 400万円 | 1,200万円 | 16.8万円 | 3.6万円 | 20.4万円 |
※上記は目安です。評価額や課税標準の特例適用で大きく変動します。
4-2: 固定資産税のシミュレーションツールの活用法
固定資産税は各市区町村の公式サイトや民間の不動産ポータルで無料のシミュレーションツールが多数用意されています。
主なツール・サービス
【自治体公式】「◯◯市 固定資産税 シミュレーション」で検索
【民間】LIFULL HOME’S、SUUMO、不動産会社サイト等
【最新】GX住宅・ZEH住宅などエコ住宅の減税自動計算機能付きも登場
【使い方アドバイス】
物件の種類(戸建/マンション)、延床面積、土地面積、築年数、エリアなどを入力すると、おおよその固定資産税額が自動算出されます。注意点:軽減措置・特例・評価額改定による年次変動はツール上では再現できない場合も。最終的な納税額は自治体の通知書を必ず確認しましょう。
4-3: 年ごとの変動に注意するべきポイント
■ 固定資産税は毎年変動する
評価額は3年ごとに見直し(2025年は評価替え年)
建物は経年劣化で評価額が年々下がる(概ね築20年でほぼ最低評価)
土地は地価の上下や都市計画の変更で評価が変動
マンションは共用部の修繕や再評価で一時的に評価額が上がることも
▼ 固定資産税の変動イメージ(モデルケース:新築戸建)
築年数 | 評価額(家屋) | 年間税額(概算) |
1年目 | 1,600万円 | 22.4万円 |
5年目 | 1,200万円 | 16.8万円 |
15年目 | 600万円 | 8.4万円 |
25年目 | 300万円 | 4.2万円 |
【施主の声】
「新築時の税額は想定より高かったが、築10年以降は評価額が大きく下がり、毎年の納付額も年々減っていきました。税負担は“最初がピーク”と考えておくと良いです」(東京都・戸建オーナー)
【プロの解説】
「固定資産税は毎年定額ではなく“評価額の変動=負担の変化”が非常に大きい税金です。住宅性能やリフォーム内容によっても軽減特例が使えるため、納税額を過大評価せず必ず数年分のシミュレーションを」
5: 固定資産税の軽減措置と特例

5-1: 固定資産税の軽減措置の種類
固定資産税は、さまざまな軽減措置や特例によって初期~数年間は税負担が大幅に軽減される場合があります。GX志向型住宅・ZEH住宅の新築、認定長期優良住宅、一定面積以下の住宅地は特に恩恵が大きいです。
▼ 主な軽減措置・特例一覧(2025年版)
対象住宅 | 軽減内容 | 適用期間・条件 |
新築住宅 | 建物部分の固定資産税1/2減額 | 3年間(長期優良住宅は5年)、床面積50~280㎡ |
認定長期優良住宅 | 建物部分の固定資産税2/3減額 | 5年間、床面積50~280㎡ |
ZEH・GX住宅 | 一部自治体で追加減税・特例あり | 条件・自治体により内容異なる |
小規模住宅用地 | 200㎡以下の土地は課税標準額1/6 | 恒久措置 |
その他リフォーム | バリアフリー、省エネリフォームなど | 内容ごとに控除・減額期間が異なる |
【プロコメント】
「2025年はGX志向型住宅の推進に伴い、ZEH水準や長期優良住宅の新築時に最大5年の建物税額減免が受けられます。自治体によっては“追加の補助”も出るので要チェックです。」
5-2: 特例措置の適用条件と申請方法
適用条件例
新築(未使用)であること
床面積が50㎡~280㎡以内であること(戸建・マンション共通)
長期優良住宅等は認定を受けていること
省エネリフォーム等は工事内容・施工証明が必要
申請方法
原則として「新築後一定期間内(通常は完成後3か月以内)」に市区町村の資産税課へ申請書類・証明書を提出
長期優良住宅やZEH等は認定通知書や性能証明書、工事写真などの提出が必要
【実体験】
「新築引渡し後すぐに市役所へ行き、“長期優良住宅の認定通知書”と“建築確認済証”を提出。申請は簡単でしたが、書類の不備で一度差し戻しになりました。余裕をもって申請準備したほうが安心です。」
5-3: 負担軽減に向けた最新情報
GX志向型住宅・ZEH住宅は2025年も軽減特例の対象
長期優良住宅なら5年間、その他新築なら3年間建物税が半額
小規模住宅用地の1/6特例も引き続き適用
一部自治体で“追加減税”や補助金(固定資産税還付型など)も新設
省エネリフォームは控除額や減税期間が拡充中
注意点
申請忘れや書類不備は「軽減措置の適用外」となる
各種特例は年度・自治体によって内容が毎年変わるため、市区町村公式サイトや施工会社経由で必ず最新情報を確認
【Q&A】
Q.「GX志向型住宅の固定資産税減額は自動で受けられる?」
A.「多くの自治体では申請が必要。必要書類や期限は地域ごとに異なるので、家の完成後できるだけ早く自治体窓口に相談を。」
6: 古い家と新築住宅の税負担の比較

6-1: 古い家の固定資産税はいくらか?
古い住宅(築20年以上など)は家屋評価額が大きく下がっているため、固定資産税も年々安くなります。ただし、土地評価額は地価の変動や用途地域の変更で変動することも。
築年数 | 家屋評価額 | 土地評価額 | 合計評価額 | 固定資産税(1.4%) | 都市計画税(0.3%) | 年間納付額 |
新築 | 1,600万円 | 2,000万円 | 3,600万円 | 50.4万円 | 10.8万円 | 61.2万円 |
10年目 | 900万円 | 2,000万円 | 2,900万円 | 40.6万円 | 8.7万円 | 49.3万円 |
20年目 | 400万円 | 2,000万円 | 2,400万円 | 33.6万円 | 7.2万円 | 40.8万円 |
【一次情報】
「築30年以上の中古戸建に住んでいますが、固定資産税は家屋部分がほぼゼロ評価で、土地だけの負担になりました。年6万円台にまで下がっています」(大阪市・60代男性)
6-2: 新築住宅の固定資産税の特徴
新築住宅の最大の特徴は最初の3年間(長期優良住宅等は5年間)、建物部分の固定資産税が1/2または2/3に軽減されることです。GX志向型住宅やZEH住宅など高性能住宅は長期優良住宅認定による5年間の2/3減額も受けやすいのが特徴です。
新築時は家屋評価額が高く、最初の納付額が「想像より高い」と感じることも
軽減措置終了後(4年目または6年目)は税負担が一気に増えるため要注意
経年で評価額が下がり、築15年~20年で家屋部分の負担は激減
【体験談】
「新築戸建は初年度、軽減後でも年12万円超でした。4年目以降は倍近くになり驚きましたが、築10年を超えると負担が徐々に減っていきました」(千葉県・40代夫婦)
6-3: 経年による評価額の変動とは?
固定資産税の評価額(特に家屋)は築年数によって年々下がり、20~25年でほぼ最低水準になります。一方、土地は地価や再開発・都市計画の影響で上下しますが、「家屋負担の減少」が持ち家の長期的な税コスパのポイントです。
▼ 家屋評価額の経年変動グラフ(例)
築年数 | 評価額 | 税額目安(1.4%) |
新築 | 1,600万円 | 22.4万円 |
5年目 | 1,200万円 | 16.8万円 |
10年目 | 900万円 | 12.6万円 |
15年目 | 600万円 | 8.4万円 |
25年目 | 300万円 | 4.2万円 |
※土地評価額は別途加算
【プロ視点】
「持ち家の固定資産税は、“最初が一番高く、その後は右肩下がり”が基本。リフォームや増築、耐震補強等で一時的に評価が上がるケースもありますが、一般的には20~25年で“家屋部分の負担感”はかなり小さくなります」
【Q&A】
Q.「築古住宅と新築住宅の固定資産税、どちらが得?」
A.「初期負担を抑えたいなら築古、軽減特例や断熱・耐震など省エネ住宅の優遇を受けたいなら新築もおすすめ。将来の売却や相続を考え、長期視点で判断しましょう」
7: 固定資産税の支払い方法と納付時期

7-1: 納税通知書の確認ポイント
毎年4月~6月頃に自治体から「固定資産税納税通知書」が郵送されます。この通知書には課税明細書/納付書/評価額や税額の内訳が記載されているため、必ず内容をチェックしましょう。
▼ チェックするべきポイント
土地・家屋ごとの評価額と課税標準額
軽減特例や減免の適用有無
納付期限と納付方法
分割納付(4期分割が多い)か一括納付か
都市計画税などの加算額
【ヒント】
「通知書の“軽減適用期間”や“終了年度”は見落としがち。特例の終了時期を見て、次年度以降の税額アップに備えるのが大切です」
7-2: 各種納付方法のメリット・デメリット
2025年現在、固定資産税の納付方法は多様化しており、現金・キャッシュレス・口座振替などが選べます。それぞれのメリット・デメリットを理解し、自分に合った方法を選びましょう。
納付方法 | メリット | デメリット |
コンビニ納付 | 全国の主要コンビニで手軽・夜間もOK | 納付書のバーコード有効期限がある |
金融機関窓口 | 高額納付もOK、領収書が確実に手元に残る | 営業時間・混雑時は手間 |
口座振替 | 手間なし・払い忘れ防止 | 口座残高不足だと未納になる |
クレジットカード納付 | ポイントが貯まる・ネットから簡単決済 | 手数料がかかることが多い |
ペイジー/スマホ決済 | スマホから24時間納付OK、即時反映 | 端末操作に慣れが必要、自治体によって非対応も |
【プロコメント】
「2025年はほぼ全自治体で“スマホ納付(PayPay・LINE Pay等)”が使えます。ポイント還元を狙いたい人はクレジット納付・スマホ納付の活用が増えていますが、納付期限や手数料には必ず注意を」
7-3: 期限の重要性と支払い時期の確認
固定資産税は年1回一括、または4期分割(各期約3か月ごと)で納付が基本。支払い期限を過ぎると「延滞金(年8.7%相当/2025年時点)」が課されるため、必ず納付期限までに支払いを済ませましょう。
▼ 固定資産税の納付スケジュール(例)
期別 | 納付期限(例) | 主な注意点 |
第1期 | 5月31日 | 初回通知後の支払い忘れが多い |
第2期 | 8月末 | 夏の帰省・旅行時は注意 |
第3期 | 11月末 | 年末で支出が多く忘れがち |
第4期 | 翌年2月末 | 確定申告と重なる時期 |
【体験談】
「分割納付で毎回コンビニ払いにしていますが、旅行や出張で納付を忘れそうになることも。スマホアプリで納付期限のアラート機能を活用しています」(東京都・マンションオーナー)
【Q&A】
Q.「支払いを忘れたらどうなる?」A.「延滞金が加算され、督促状が届きます。長期未納の場合、財産差押えなど法的手続きも。必ず期限内納付を」
8: まとめと今後の固定資産税の流れ
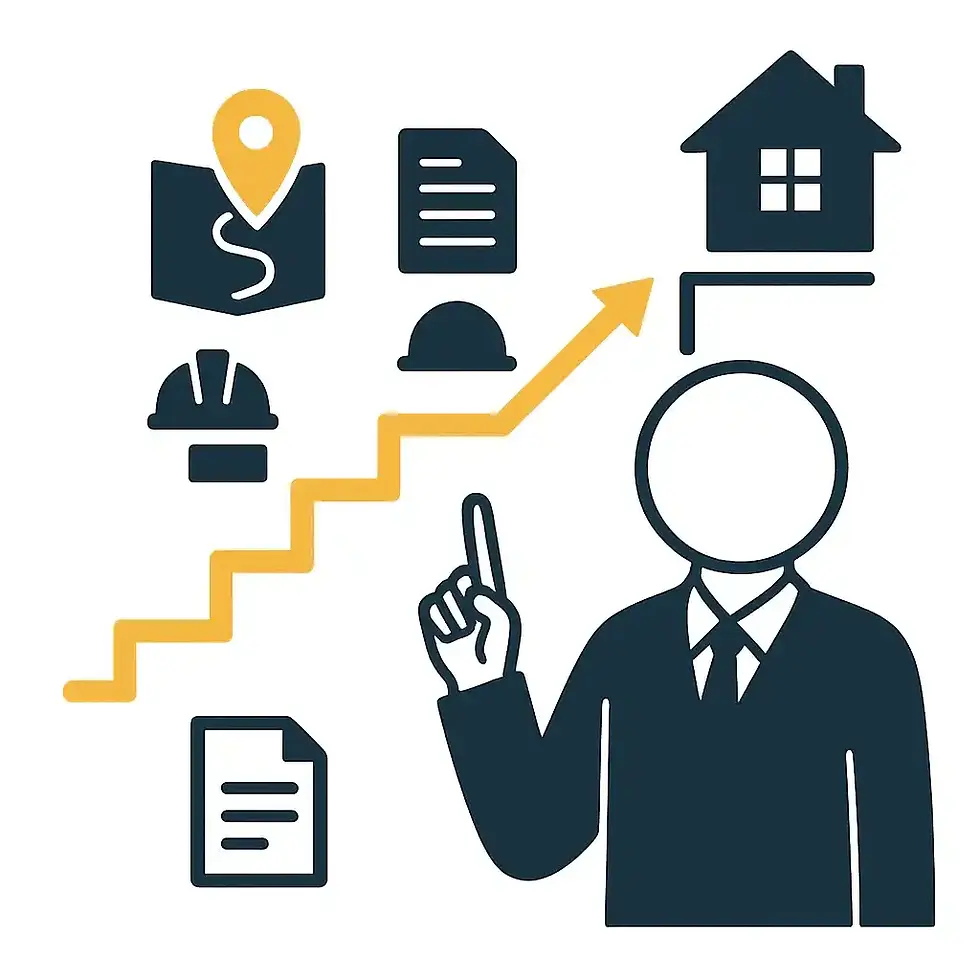
8-1: 理解しておくべき固定資産税の基礎知識
固定資産税は、家や土地を所有する限り毎年必ず発生する税金です。「課税標準額×税率(1.4%)」が基本ですが、自治体による都市計画税(0.3%等)の上乗せや、新築・長期優良住宅・小規模住宅地など各種軽減措置・特例を活用することで、数年間は負担を大きく減らすことができます。
家屋は築年数の経過で評価額が下がり、税額も年々下がる傾向
軽減特例や控除は申請・手続きの“忘れ”に注意
納税通知書で税額や適用期間を毎年確認することが大切
【ヒント】
「住宅ローンや火災保険と違い、“固定資産税”は“住んでみて初めて実感する負担”という声が多いです。長期的に見てどの時期にいくら納税するのか、家計計画に必ず組み込んでおきましょう」
8-2: 一戸建て、マンションの税負担を見直す
一戸建てとマンションでは評価額や課税の仕組みが微妙に異なり、特に土地の持分や共用部の扱いがポイント
新築時はどちらも軽減措置が受けられるが、経年で負担が下がるペースや築古物件の“土地だけ課税”への移行タイミングも違う
GX志向型住宅やZEH住宅など高性能住宅は、認定や性能による追加の優遇措置や各自治体の独自支援を受けやすい
築古マンションは「修繕後の評価額アップ」にも注意
土地評価は都市開発や再開発、地価の動向に左右される
住宅タイプ | 初年度税額(目安) | 20年後税額(目安) |
新築戸建 | 12万円〜22万円 | 5万円〜8万円 |
新築マンション | 8万円〜15万円 | 3万円〜7万円 |
築30年戸建 | 4万円〜6万円 | 4万円〜6万円 |
築30年マンション | 2万円〜5万円 | 2万円〜5万円 |
【専門家コメント】
「一戸建てとマンション、どちらが得かは“短期の軽減特例”か“長期の地価や建物価値の変化”かで変わります。10年後、20年後の資産価値や税コストも含めた“ライフプラン全体”で判断することがポイントです。」
8-3: 将来の計画に向けた影響を考える
2025年以降、GX志向型住宅や省エネ基準の住宅の普及に合わせて、固定資産税の軽減特例や補助金、さらなる税制優遇が拡大・強化される流れです。
GX住宅・ZEH住宅の優遇措置が延長・拡充される可能性大
高齢化社会・空き家問題を背景に、「築古住宅の税負担見直し」「リフォーム・耐震補強への減税強化」も今後の焦点
2040年に向けて「GX住宅普及率5割」の政府目標などにより、将来的には「省エネ住宅が“普通”」になる可能性
デジタル納付やマイナンバー連動で納税・証明の手続きもますます簡素化
【Q&A】
Q.「GX住宅にすれば今後も税金が安くなる?」
A.「省エネ性能の高さや認定制度の利用で軽減策・補助金の恩恵は大きいです。今後も優遇策が続く見込みですが、最新情報の確認と適切な申請が不可欠です。」
\➡ 関連記事:価格上昇の要因は?ハウスメーカー坪単価推移を徹底解説
まとめ:固定資産税は“制度・家計・未来”を見据えて柔軟に
新築・GX志向住宅・ZEH住宅は“税優遇の追い風”を最大活用
築古住宅も長期でみれば負担減。リフォーム等の新たな特例に注目
一戸建てもマンションも「税・資産価値・ライフプラン」を総合的に考えた住まい選びが、将来後悔しない最大のポイント
-26.webp)

-39-2.webp)

