戸建ての維持費シミュレーション!平均額と内訳を徹底解説
- 見積もりバンク担当者

- 2025年9月7日
- 読了時間: 16分
更新日:2025年11月2日
更新日:2025年11月02日
マイホームを購入するとき、多くの人が住宅ローンの返済額ばかりに注目してしまいがちです。しかし、実際には「維持費」という継続的な出費が家計に大きな影響を与えます。固定資産税、火災・地震保険、水道光熱費、修繕・メンテナンス費用……これらを正しく把握していなければ、思わぬ出費で生活を圧迫し、後悔することになりかねません。
本記事では、**「戸建て 維持費 シミュレーション」**をテーマに、平均額や内訳をデータとともに解説。さらに、地域別・新築と中古別の違い、節約のための具体策、実際に維持費が膨らんだ事例とその対策など、2025年最新情報を反映して徹底解説します。記事後半では、シミュレーションツールの紹介や資金計画に役立つチェックリストも掲載。これを読めば、一戸建て購入後の資金不安を解消し、安心してマイホーム生活をスタートできるはずです。

目次
2-1. 維持費の基本的な内訳
2-2. 戸建てとマンションの維持費比較
2-3. 一軒家の維持費を理解する重要性
3-1. 年間の維持費の目安
3-2. 毎月の出費を把握する方法
3-3. 過去30年の維持費の変動
4-1. 固定資産税と保険料の試算
4-2. 修繕費の計算方法と目安
4-3. 水道光熱費の予測
5-1. 定期点検の重要性とタイミング
5-2. メンテナンスのコストを抑える方法
5-3. 省エネ設備の活用
6-1. マイホーム購入後の注意点
6-2. 修繕しないリスク
6-3. 事前に知っておくべき出費の考慮事項
7-1. 毎月の支出を見える化する方法
7-2. 長期的なコストを考慮した プランニング
7-3. 自治体や保険会社からの軽減措置の活用
8-1. 都市と郊外での維持費の違い
8-2. 新築と中古の維持費比較
8-3. 特定エリアで注意すべきポイント
9-1. 固定資産税評価額の計算方法
9-2. 都市計画税とその影響
9-3. 軽減措置の活用法

戸建ての維持費を考えるうえで役立つのが「シミュレーションツール」です。住宅金融支援機構や自治体が提供する公式シミュレーターに加え、最近では不動産ポータルサイトや民間サービスでもオンラインで試算できるサービスが増えています。これらを活用することで、購入前に現実的な維持費を把握し、資金計画を具体化することが可能です。

マイホームを購入すると、住宅ローン返済だけでなく、毎年必ず発生する維持費が家計を圧迫することになります。ここでは一戸建てにおける維持費の基本構造や、マンションとの違いを整理しておきましょう。
2-1: 維持費の基本的な内訳
戸建ての維持費は、大きく以下の4つに分類されます。
税金関連
固定資産税・都市計画税が中心。評価額によって変わり、築年数が経つにつれて徐々に下がるケースもある。
保険料
火災保険や地震保険が代表的。自然災害が多い日本では必須の維持費。
修繕・メンテナンス費
屋根や外壁、設備交換、シロアリ対策など。計画的に積み立てないと急な出費につながる。
光熱費・水道代
電気、ガス、水道などのランニングコスト。家族人数や設備仕様によって大きく変動する。
👇 あわせて読みたい関連記事
2-2: 戸建てとマンションの維持費比較
「戸建てとマンションではどちらが維持費が高いのか?」という疑問は多くの人が抱きます。
項目 | 戸建て | マンション |
固定資産税 | 土地・建物分で発生 | 建物共有部分含むが土地持分は少なめ |
修繕費 | 自己責任で積立 | 管理組合で計画的に積立金徴収 |
管理費 | 基本的に不要 | 管理費・共益費として毎月必要 |
保険 | 火災・地震保険は必須 | 同じく必須だが建物の耐震性で金額差 |
2-3: 一軒家の維持費を理解する重要性
維持費を軽視して購入すると、10年後に修繕が必要になった際に家計を圧迫する。
維持費の実態を把握していれば、「賃貸に住み続ける場合」との比較が可能になり、住宅購入の判断がより現実的になる。
維持費を予測し、毎月積立を行うことが「安心して暮らすための必須条件」といえる。
プロ視点のアドバイス
営業現場では「ローン返済は払えても、維持費でつまずいた」という声をよく耳にしました。特に外壁塗装や屋根工事は数百万円単位の費用がかかるため、事前に積み立て計画を立てている人とそうでない人の差は歴然です。購入前に必ず「維持費を含めた家計シミュレーション」を行いましょう。

「戸建てを購入すると、年間いくら維持費がかかるのか?」は多くの方が最も気になるポイントです。ここでは国や住宅金融支援機構、実際のオーナーのデータをもとに、平均的な維持費の実態を整理します。
3-1: 年間の維持費の目安
国土交通省や住宅金融支援機構の調査によると、一戸建ての年間維持費はおおよそ20万〜40万円程度が目安とされています。
固定資産税・都市計画税:10万〜20万円
火災・地震保険料:3万〜7万円
修繕・メンテナンス:5万〜15万円(長期的にはさらに増加)
水道光熱費:年間60万〜80万円(家族4人・オール電化想定)
👇 あわせて読みたい関連記事
3-2: 毎月の出費を把握する方法
年間で見ると金額が大きく感じられますが、月単位に換算することで計画的に準備できます。
例:年間30万円の維持費 → 月あたり2.5万円を積み立て
ボーナス時にまとめて支払う方法もあり
家計簿アプリや住宅費専用口座を活用すると管理がスムーズ
💡 チェックリスト:毎月の維持費管理に必要なこと
固定資産税を毎月分割積立する
火災保険更新時期をカレンダー管理
10年後に外壁修繕費用を準備しておく
3-3: 過去30年の維持費の変動
日本の住宅維持費は、過去30年で以下のような傾向を見せています。
1990年代:建材の劣化が早く、修繕費が高め
2000年代:高性能住宅が普及し、断熱材・外壁の耐久性向上
2010年代以降:省エネ住宅や長期優良住宅により修繕間隔が伸びた
2020年代〜:自然災害の増加により地震保険・火災保険料が上昇傾向
プロ視点のアドバイス
平均値だけでなく、築年数ごとの維持費の増加カーブを意識することが大切です。築10年を超えると外壁塗装、築20年を超えると屋根や水回りリフォームなどが必要になるケースが多く、**「購入直後よりも10年後以降の維持費が増える」**と考えておくと安心です。
👇 あわせて読みたい関連記事

維持費は「なんとなく」で計算すると、実際の出費と大きく乖離してしまいます。ここでは、具体的なシミュレーション方法を通じて、戸建ての維持費を現実的に把握するステップを解説します。
4-1: 固定資産税と保険料の試算
固定資産税は、土地・建物の評価額 × 1.4%(標準税率)で算出されます。また、都市計画税(0.3%)がかかる地域もあります。
例:評価額2,000万円(建物1,200万+土地800万)の場合
固定資産税:28万円
都市計画税:6万円
合計:約34万円/年
さらに火災保険・地震保険を加えると、年間40万円前後になるケースも。
4-2: 修繕費の計算方法と目安
修繕費は「築年数×㎡単価」でおおよその目安が立てられます。国土交通省の調査によると、戸建ての修繕・リフォーム費用は30年間で600万〜900万円程度。
外壁塗装:100万〜150万円(10〜15年ごと)
屋根修繕:80万〜120万円(20年ごと)
水回りリフォーム:100万〜200万円(20〜30年ごと)
💡 修繕積立シミュレーション例(築30年/延床120㎡)
毎年10万円を修繕積立すると、30年後に300万円確保
実際には不足する可能性があるため、15万円/年ペースが理想
4-3: 水道光熱費の予測
一戸建ての光熱費は、家族構成・地域・設備仕様によって変動します。
家族4人(オール電化・省エネ住宅)の場合:月2.5万〜3.5万円
ガス+電気併用住宅:月3万〜4万円
高気密・高断熱住宅:月1.8万〜2.5万円
さらに電気代は2022年以降のエネルギー価格上昇で増加傾向にあります。最新の省エネ設備(太陽光発電・高効率給湯器など)を導入すると、光熱費を年間10万〜20万円削減できる可能性もあります。
プロ視点のアドバイス
維持費は「固定資産税+保険料+修繕費+光熱費」をセットで計算するのが基本です。特に、修繕費と光熱費は将来のライフスタイルに直結するため、10年単位での予測をおすすめします。
👇 あわせて読みたい関連記事

戸建ての維持費は、正しく管理すれば大きく抑えられます。ここでは、固定費から修繕費まで賢く節約する具体策を解説します。
5-1: 定期点検の重要性とタイミング
維持費の中で大きな割合を占めるのが修繕費です。放置すれば数百万円単位のリフォームに発展するケースも。
外壁・屋根
→ 10年ごとに点検
水回り(浴室・キッチン)
→ 5年ごとに点検
設備(給湯器・エアコン)
→ 7〜10年で交換目安
💡 節約ポイント
小さな不具合を早期に直せば、修繕コストを半分以下に抑えられる可能性があります。
👇 あわせて読みたい関連記事
5-2: メンテナンスのコストを抑える方法
日常的なメンテナンスを工夫することで、出費を最小限にできます。
DIYでできる補修
→ 壁紙の剥がれ、簡単な水漏れ修理
消耗品交換を自分で行う
→ フィルター、パッキン
複数工事をまとめて依頼
→ 足場設置費を節約
📌 チェックリスト:メンテナンス費を減らす工夫
□ 小さな故障は早期に修理
□ 定期的な掃除で設備寿命を延ばす
□ まとめ工事で割引交渉
👇 あわせて読みたい関連記事
5-3: 省エネ設備の活用
省エネ設備の導入は、光熱費の節約+補助金の活用で大きな効果を発揮します。
太陽光発電+蓄電池
→ 年間15万〜20万円の電気代削減
高断熱サッシ・断熱材強化
→ 冷暖房費を20〜30%削減
高効率給湯器(エコキュートなど)
→ 年間3万〜5万円節約
さらに2025年は「住宅省エネ2025キャンペーン」などの補助制度も継続予定。初期費用は高くても、10〜15年で回収可能な投資といえます。
プロ視点のアドバイス
節約のコツは「先延ばしをしないこと」。不具合を放置すると、数倍の修繕費が必要になります。加えて、補助金や助成金を上手に利用することで、省エネ設備の導入コストを抑えるのも重要です。

マイホームを購入するとき、多くの人が見落としがちなのが「維持費の現実」です。購入後に「こんなにお金がかかるとは思わなかった」と後悔するケースは少なくありません。本章では、実際にかかる費用や失敗事例をもとに、購入前に知っておくべきポイントを整理します。
6-1: マイホーム購入後の注意点
新築時は快適ですが、10年、20年と経過するうちに維持費は増加します。
外壁塗装:10〜15年ごとに約100万〜150万円
屋根リフォーム:20〜30年で約150万〜250万円
水回りリフォーム(浴室・キッチン):20年で約100万〜200万円
📌 注意すべき落とし穴
「住宅ローン返済だけ考えていたら維持費が払えない」
「初期に外構や太陽光を妥協して、後から高額出費になった」
6-2: 修繕しないリスク
修繕を後回しにすると、単に住みにくくなるだけでなく、資産価値の低下や売却時の査定減額にも直結します。
外壁クラック放置
→ 雨漏りで木材腐食 → 大規模修繕が必要
給湯器を放置
→ 突然の故障で生活停止+緊急交換費用UP
定期点検を怠る
→ 保険適用外のケース多数
💡 事例
築15年で外壁塗装を先延ばし → 築20年で雨漏り → 修繕費400万円超に。
6-3: 事前に知っておくべき出費の考慮事項
維持費は「いつ・どれくらいかかるか」をシミュレーションしておくことが重要です。
📊 一戸建て維持費のタイムライン例(30年間)
築年数 | 想定される出費 | 金額目安 |
5年 | 設備点検・軽微修繕 | 5〜10万円 |
10年 | 外壁・屋根点検、部分修繕 | 30〜50万円 |
15年 | 外壁塗装 | 100〜150万円 |
20年 | 水回りリフォーム | 150〜250万円 |
30年 | 屋根全面リフォーム | 200〜300万円 |
👉 維持費を「計画的に積立てる」ことが後悔回避の最大のコツです。
プロ視点のアドバイス
「維持費を予測して準備する人」と「行き当たりばったりで支払う人」とでは、30年後に数百万円の差が出ます。住宅ローンと同じくらい、維持費の積立を家計に組み込んでおくことが、安心して暮らす鍵です。

戸建ての維持費は「毎月の出費」として目に見えにくいため、ローン返済だけを考えてしまいがちです。しかし実際には、修繕や税金の支払いのために計画的な資金管理が必須です。本章では、維持費を無理なく管理するための具体的な方法を解説します。
7-1: 毎月の支出を見える化する方法
維持費を計画的に管理するためには、「毎月の家計簿」に維持費積立を組み込むのが最も有効です。
📌 実践ステップ
家計簿アプリやエクセルで維持費用の「積立枠」を設定
固定資産税・保険料・修繕費を年換算 → 月割りして積立
光熱費や水道代の変動を記録 → 平均値を維持費に加算
💡 例
固定資産税年12万円 → 月1万円積立
修繕積立年30万円(外壁・屋根等) → 月2.5万円積立
火災保険料年6万円 → 月5,000円積立
7-2: 長期的なコストを考慮したプランニング
戸建ては築年数が経つにつれ修繕費が増えるため、30年・40年スパンでの資金計画が必要です。
📊 30年間でかかる費用シミュレーション例(4人家族・延床30坪)
項目 | 10年間 | 20年間 | 30年間 | 合計 |
固定資産税・都市計画税 | 120万円 | 240万円 | 360万円 | 720万円 |
火災・地震保険 | 60万円 | 120万円 | 180万円 | 360万円 |
外壁・屋根修繕 | 100万円 | 250万円 | 200万円 | 550万円 |
水回りリフォーム | – | 150万円 | 200万円 | 350万円 |
その他修繕 | 30万円 | 50万円 | 70万円 | 150万円 |
合計 | 310万円 | 810万円 | 1,010万円 | 2,130万円 |
👉 家族構成や地域によって差はありますが、30年で約2,000万円以上の維持費がかかることも珍しくありません。
7-3: 自治体や保険会社からの軽減措置の活用
維持費を少しでも抑えるためには、補助金や軽減制度をフル活用することが大切です。
✅ 活用できる代表例
長期優良住宅認定
→ 固定資産税の軽減(5年間1/2)
省エネ住宅ポイント制度
→ リフォーム費用の補助
自治体の耐震改修補助金
→ 工事費用の一部を助成
保険会社のセット割
→ 火災+地震保険加入で割引
プロ視点のアドバイス
「家計の中で『住宅ローン+維持費積立』をセットで考える」ことが成功の秘訣です。維持費は突然発生する大きな出費を平準化できるかどうかで安心感が大きく変わります。

一戸建ての維持費は、立地や建物の種類によって大きく異なります。ここでは、都市部と郊外、新築と中古、さらには地域ごとの傾向を比較しながら、維持費の違いを解説します。
8-1: 都市と郊外での維持費の違い
都市部と郊外では、固定資産税や修繕コストに大きな差があります。
📊 都市部と郊外の維持費比較(例:東京23区 vs 地方都市)
項目 | 都市部(東京23区) | 郊外(地方都市) |
固定資産税・都市計画税 | 年15〜25万円 | 年7〜15万円 |
火災・地震保険 | 年8〜12万円(地震リスク高) | 年4〜8万円 |
修繕・リフォーム費 | 高額(人件費・資材費が高い) | 比較的安い |
光熱費 | 同程度 | 同程度 |
👉 都市部は 土地評価額の高さと人件費により維持費が割高になりやすいのが特徴です。
8-2: 新築と中古の維持費比較
建物の築年数によって、修繕にかかる費用は大きく異なります。
📌 新築のメリット
10年間は大規模修繕が少ない
保証制度(住宅瑕疵担保責任保険など)が適用される
📌 中古住宅の注意点
築15年以上で水回り交換・外壁修繕が必要になるケース多数
見た目が綺麗でも内部設備が老朽化している可能性
💡 中古住宅を購入する場合は、リフォーム費用を維持費として組み込むことが不可欠です。
👇 あわせて読みたい関連記事
8-3: 特定エリアで注意すべきポイント
地域特性によって、維持費のかかり方は異なります。
✅ 地域別の維持費注意点
北海道・東北地方
→ 暖房費(灯油・電気)が年間20〜30万円増加
沿岸部(太平洋側・沖縄など
→ 塩害による外壁・屋根の劣化が早く修繕費UP
地震多発地域(関東・東海)
→ 地震保険料が全国平均の1.5〜2倍
豪雪地帯(新潟・北陸)
→ 屋根の雪下ろし・補強費用が発生
プロ視点のアドバイス
「購入エリアを決める前に、固定資産税・保険料・気候による修繕リスクを試算することが大切です。建物価格が安くても、維持費が高ければトータルコストは割高になるケースがあります。」

一戸建ての維持費の中で大きな割合を占めるのが 固定資産税・都市計画税 です。これらは土地や建物を所有する限り毎年必ず発生するため、長期的な資金計画には欠かせません。ここでは、税金の仕組みや軽減措置について詳しく解説します。
9-1: 固定資産税評価額の計算方法
固定資産税は、固定資産税評価額 × 1.4%(標準税率) で算出されます。
📌 計算例
建物評価額:1,500万円
土地評価額:2,000万円
合計評価額:3,500万円
固定資産税:3,500万円 × 1.4% = 49万円/年
👉 実際
住宅用地特例や軽減措置があるため、ここまで高額にはなりません。
9-2: 都市計画税とその影響
都市計画税は、都市計画区域内の土地・建物に課税される税金で、評価額 × 0.3%(上限) が基準です。
例:評価額3,500万円の場合 → 年額 10.5万円
📍 ポイント
都市計画区域外の住宅には課税されない
大都市圏や政令指定都市では必ず発生
9-3: 軽減措置の活用法
新築一戸建ての場合、一定期間は税額が軽減されます。
✅ 新築住宅の固定資産税軽減特例
住宅の床面積:50㎡〜280㎡が対象
新築後3年間、税額が 1/2に軽減
長期優良住宅の場合 → 軽減期間が 5年間
✅ 住宅用地の特例
小規模住宅用地(200㎡以下):課税標準額が 1/6に軽減
一般住宅用地(200㎡超):課税標準額が 1/3に軽減
📊 税額イメージ比較(都市部・床面積100㎡の住宅の場合)
項目 | 軽減前 | 軽減後(1〜3年目) |
固定資産税 | 約20万円 | 約10万円 |
都市計画税 | 約5万円 | 約2.5万円 |
合計 | 約25万円 | 約12.5万円 |
プロ視点のアドバイス
「新築直後は軽減措置で税額が抑えられますが、4年目以降は急に維持費が増える点に注意が必要です。ローン返済と並行して、固定資産税分の積立をしておくと安心です。」
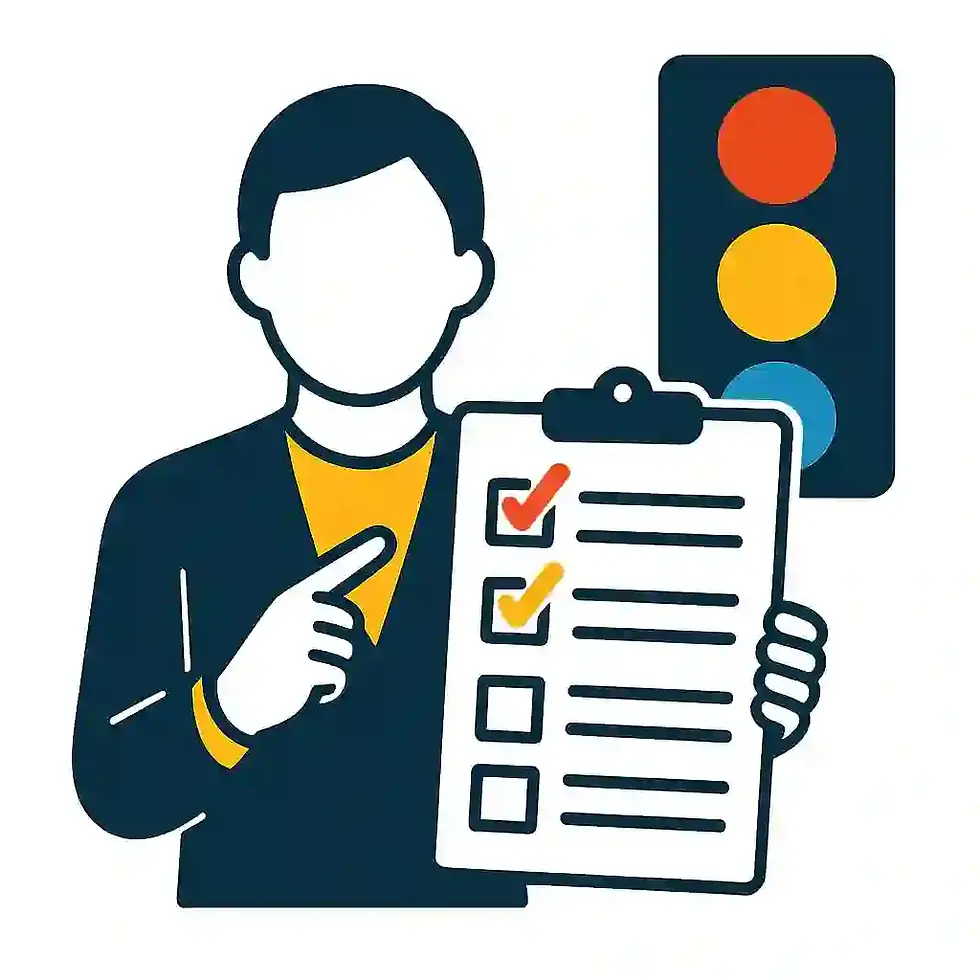
ここまで、一戸建ての維持費について「内訳」「平均額」「節約方法」「税金の仕組み」などをシミュレーションを交えながら解説してきました。最後に重要なポイントを整理して、読者が実生活で役立てられるようにまとめます。
10-1: 戸建て維持費の全体像を把握する
一戸建ての維持費は、固定資産税・都市計画税・保険料・修繕費・光熱費 など多岐にわたります。特に見落とされがちなのが 突発的な修繕費。外壁や屋根、水回りの修繕は数十万円規模になりやすく、定期的な積立が欠かせません。
👉 年間の維持費目安は、新築で20万〜40万円、中古で30万〜60万円 が一般的です。
10-2: 維持費を抑えるための工夫
省エネ設備の導入(太陽光発電・断熱窓・高効率給湯器)
計画的メンテナンス(小さな不具合を早めに修理)
補助金・税制優遇の活用(長期優良住宅・ZEH対応など)
これらを意識することで、10年単位で数百万円の節約につながる可能性があります。
👇 あわせて読みたい関連記事
10-3: 将来を見据えた資金計画の重要性
一戸建ては建てて終わりではなく、「住んでからが本番」です。特にローン返済と並行して維持費が発生するため、毎月の固定費+将来の修繕費積立を両立させることが重要です。
✅ 実践アドバイス
毎月の家計に「維持費積立」を組み込む
固定資産税の納付時期に合わせて積立口座を管理
10年ごとに修繕計画を立てて費用を見える化
10-4: 最後に
一戸建ての維持費は、しっかりと把握して準備しておけば「突然の大出費」に慌てるリスクを減らせます。今回のシミュレーションや解説を参考に、 「購入前に維持費を具体的にイメージする」ことこそ、後悔しないマイホーム計画の第一歩 です。
📌 プロ視点からのまとめ
「家づくりは“建てる費用”だけでなく、“住み続ける費用”の把握が成功のカギです。維持費を具体的に数値化し、補助金や省エネ設備も活用しながら、安心して長く住める家計プランを作りましょう。」
-26.webp)

-39-2.webp)


